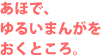
これでさいごだ。
この世界ったら、なんて素敵なんでしょう!
そんなことを叫び出したい気分だった。歌って踊って笑いたかった。それぐらいにその時のわたしはしあわせだった。
先生のとこに行ってみる気になったのは、きっとそのしあわせに浮かれてしまったからだろう。
宇宙船に近づくとピアノの音が聞こえてきた。足音をたてないよう、そろりと入り口に立つ。優しげな音色を奏でる先生になんだか声はかけづらく、しばらくその後ろ姿を見つめていた。
そのうちふわふわした気持ちは落ち着いてきて、なんとはなしに虚しくなってしまった。
(もう、いいや)
ひとつ浅いため息をついてきびすを返す。そうしたらその音が聞こえたのか、先生の機械音のような声がわたしを呼び止めた。振り返ると、いつものようにちぐはぐな目をした顔がこちらを見ていた。
「こんにちは、せんせ」
にへら、反射みたいにして笑みをこぼす。いつもなら包丁のひとつでも出して怯える先生を見て楽しむのだけど、そんな気分でもなくなってしまった。
「なにをしにきたっていうわけでもないの。もう、帰るね」
もういいの。もう、いいんだ。
ピロリ、わたしには分からない、先生の言葉。その響きがどこかさみしそうな色を含んでいたからくすりと笑ってしまった。
帰ろうとすると、先生の手がこちらの腕に伸びてきて、思わず身構えた。
けれどその手はわたしの腕に触れることはなかった。いくらかの迷いを見せた後、先生は手を下ろして何かを、きっとさよならのような言葉を発した。
わたしは苦く、笑う。
「ばいばい」
背中に先生の視線を感じながら、わたしは宇宙船を後にした。先生はもう、なにも言わなかった。
傘を捨てた。
これだけ、宇宙船に行くのに必要だったから捨てずにいたのだ。
「…あは、」
全ての卵を見渡すと、あのしあわせな気持ちが戻ってきた。
「は、はは、あは、」
ひきつけを起こすように笑いが込み上げてきた。わたしはしあわせものだ。世界はすてき。このすてきな世界でいちばんしあわせなのが他の誰でもない、わたしだ。
なんでだろう。唐突に思う。こんなにしあわせなのになんでだろう。この世界がすてきなら、わたしはどうして。
けれどそんなこと、もうわたしが考えるべきことじゃあない。わたしがなにかを考えたって、この世界の何一つ変わることはないのだ。
ひとしきり笑うと生理的な涙がにじむ。息をついて、指の腹でそれを拭った。
その指をそのまま頬に持っていって、むにぃとつねる。微かな痛みと共に、意識は霞んでいった。
意識はいつもどうりゆっくり浮上して、固いベッドの上で目を覚ました。
目が痛いなあと思う。朝はいつもどうりに眩しくて、なにも変わりはしないのねと諦めた。
ベランダに出るため窓を開けた。さらに強まる刺すような、朝の光。その光に視界をやられて瞬きをしたあと、そこにある物体を見て笑みをこぼした。
しろい、踏み台。金属的に光るそれは、まるで以前からそこにあったよう。それに足をかける。一段、いちだん登っていく。巡る、廻る、なにか、記憶とか。思い出すのは何か。やっぱり先生のこととかかなあ。あと、ポニ子とか、モノ江とモノ子、ああそう、死体さんも。意外とたくさん思い出すひとがいたものだ。まあ、自分の夢の中の住人ではあるのだけど。先生、せんせい。ごめんね。ねえ、あのとき、ひとつ言葉を発していれば、きっと先生はわたしの腕を掴んでくれていたでしょう。だからだよ。だからこそ言うわけにはいかなかったの、―助けて、なんて。(なんだ、わたし、助けてほしかったの?)きっと、助けてほしかった。そして先生は、みんなは、助けたかったんだ。
夢の中にいるときみたいに目をつむった。こっちでこうすると何も見えなくなってしまう。結局のところ、そういうこと。
「…さようなら」
別れの言葉をひとつ。それだけ残して、ベランダから飛び降りた。
そんなことを叫び出したい気分だった。歌って踊って笑いたかった。それぐらいにその時のわたしはしあわせだった。
先生のとこに行ってみる気になったのは、きっとそのしあわせに浮かれてしまったからだろう。
宇宙船に近づくとピアノの音が聞こえてきた。足音をたてないよう、そろりと入り口に立つ。優しげな音色を奏でる先生になんだか声はかけづらく、しばらくその後ろ姿を見つめていた。
そのうちふわふわした気持ちは落ち着いてきて、なんとはなしに虚しくなってしまった。
(もう、いいや)
ひとつ浅いため息をついてきびすを返す。そうしたらその音が聞こえたのか、先生の機械音のような声がわたしを呼び止めた。振り返ると、いつものようにちぐはぐな目をした顔がこちらを見ていた。
「こんにちは、せんせ」
にへら、反射みたいにして笑みをこぼす。いつもなら包丁のひとつでも出して怯える先生を見て楽しむのだけど、そんな気分でもなくなってしまった。
「なにをしにきたっていうわけでもないの。もう、帰るね」
もういいの。もう、いいんだ。
ピロリ、わたしには分からない、先生の言葉。その響きがどこかさみしそうな色を含んでいたからくすりと笑ってしまった。
帰ろうとすると、先生の手がこちらの腕に伸びてきて、思わず身構えた。
けれどその手はわたしの腕に触れることはなかった。いくらかの迷いを見せた後、先生は手を下ろして何かを、きっとさよならのような言葉を発した。
わたしは苦く、笑う。
「ばいばい」
背中に先生の視線を感じながら、わたしは宇宙船を後にした。先生はもう、なにも言わなかった。
傘を捨てた。
これだけ、宇宙船に行くのに必要だったから捨てずにいたのだ。
「…あは、」
全ての卵を見渡すと、あのしあわせな気持ちが戻ってきた。
「は、はは、あは、」
ひきつけを起こすように笑いが込み上げてきた。わたしはしあわせものだ。世界はすてき。このすてきな世界でいちばんしあわせなのが他の誰でもない、わたしだ。
なんでだろう。唐突に思う。こんなにしあわせなのになんでだろう。この世界がすてきなら、わたしはどうして。
けれどそんなこと、もうわたしが考えるべきことじゃあない。わたしがなにかを考えたって、この世界の何一つ変わることはないのだ。
ひとしきり笑うと生理的な涙がにじむ。息をついて、指の腹でそれを拭った。
その指をそのまま頬に持っていって、むにぃとつねる。微かな痛みと共に、意識は霞んでいった。
意識はいつもどうりゆっくり浮上して、固いベッドの上で目を覚ました。
目が痛いなあと思う。朝はいつもどうりに眩しくて、なにも変わりはしないのねと諦めた。
ベランダに出るため窓を開けた。さらに強まる刺すような、朝の光。その光に視界をやられて瞬きをしたあと、そこにある物体を見て笑みをこぼした。
しろい、踏み台。金属的に光るそれは、まるで以前からそこにあったよう。それに足をかける。一段、いちだん登っていく。巡る、廻る、なにか、記憶とか。思い出すのは何か。やっぱり先生のこととかかなあ。あと、ポニ子とか、モノ江とモノ子、ああそう、死体さんも。意外とたくさん思い出すひとがいたものだ。まあ、自分の夢の中の住人ではあるのだけど。先生、せんせい。ごめんね。ねえ、あのとき、ひとつ言葉を発していれば、きっと先生はわたしの腕を掴んでくれていたでしょう。だからだよ。だからこそ言うわけにはいかなかったの、―助けて、なんて。(なんだ、わたし、助けてほしかったの?)きっと、助けてほしかった。そして先生は、みんなは、助けたかったんだ。
夢の中にいるときみたいに目をつむった。こっちでこうすると何も見えなくなってしまう。結局のところ、そういうこと。
「…さようなら」
別れの言葉をひとつ。それだけ残して、ベランダから飛び降りた。