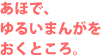
いらない
あなた、どうして消えないの。
それこそ消えそうな、か細い声で彼女は言う。だらんと下げられた手には力なく包丁が握られ、それは鈍く剣呑な光を放っている。
君こそ、どうしたの。
私は問う。果たして、この声は彼女に届いているんだろうか。
「せんせぇ」
舌っ足らずの甘い声。
振り向くと、部屋の入り口に少女がちょこんと立っていた。いつものとおり両目をつむっていて、どうやって前を見ているのだろうかと不思議に思う。私が言えたことではないけれど。
「まーた来ましたよぅ」
いかにも、無邪気といったふうにまどつきさんは笑う。いらっしゃいと言う前に私はぎょっとして飛び退いた。
きらきら笑う彼女の両手には、なんていうことだ、赤黒く錆びた包丁が握られていたのだ。
あれは痛い。刺されるとこの世の物ではないというぐらいに痛い。身を持って痛感した私が言うのだから間違いない。
私は首を振ってそれは嫌だと示したのに、まどつきさんは包丁をしまうどころか突きつけてきた。彼女は楽しんでいる。間違いない。
「なんで逃げるんですかぁ」
きゃっきゃっとはしゃぐ彼女は必死な私を追いかけてくる。なんでなんて分かっているくせに、分かっているくせに!
どん、後ろから強く押され私は地面に突っ伏してしまう。こんな少女に、情けないとも思うが今はそんなことを嘆く暇は無い。
彼女は私の上にぽすんと座り、包丁の切っ先を私の心の臓にそっと当てる。
ああ、もう駄目だ、捕まってしまった。
刺される。覚悟して、目を固く閉じ冷たい痛みを待った。しかし、いつまで待っても痛みはやってこない。不審に思いながら、私はそっと目を開けた。
下から見上げた彼女は、先程の楽しそうな様子が嘘のように表情を消していた。
「傷、消えたのね」
小さく彼女は呟く。恐らく、彼女がこの前私を刺した傷のことだろう。先生、知ってた? まどつきさんは私に問う。
「ねぇ、わたしね、先生のこと殺してしまいたいって思ってるよ」
先生を刺すのは簡単すぎてつまらないと彼女は笑んだ。
「でも先生、先生は死なないでしょう。心臓を刺したって、どこを何度刺したって。だから私、どうしようもないのだわ」
顔をくしゃりと歪めて言い放つ。その表情がなんだかとても辛そうで、どこか痛いのだろうかと心配になった。見たところ怪我なんかはしておらず、けれど表情は苦しそうだ。どうしたらよいか分からず、とりあえず彼女の頬に手を添える。
まどつきさんは思わずといったふうに両目を開いた。
頬が微かに震えている。彼女の持ち上げられていた両手が両脇に下がる。
「…どうして」
俯いた彼女から、声がこぼれておちた。泣いているのかと、思う。
「あなた、どうして消えないの」
それこそ消えそうな、か細い声で彼女は言う。
君こそ、どうしたの。
私は問う。まどつきさんは黙って首を横に振った。
果たして、届いたのだろうか。
「どうして、どうして、先生は消えてくれないの。わたし、いらないのよ、先生なんか」
どうして、なんで。彼女はそればかり繰り返す。
「いらない、いらない、いらない!!」
突如、強烈な痛みが走って私は呻いた。まどつきさんが包丁を私の胸に突き立てたからだった。じわり、血がにじむ。
「いらないの」
ぽたり、なにか、冷たいものが降ってきた。もどかしいことに、目が霞んで彼女の顔がよく見えない。
ぐるぐる、世界はまわる。その中で、まどつきさんの声だけがいやにはっきり聞こえていた。
「私に優しい人なんていらないわ」
だって、どうせ嘘なんでしょう。
だって、どうせ裏切るんでしょう。
だから先生は嫌いなひとだ。先生は、わたしにとっていらないひとだ。
いらないひと、なのに、どうして?
「どうして、わたしの夢にいてくれるの」
あなたなんかがいてくれたら、泣きたくなってしまうじゃないか。
そう言って、彼女は両手で顔を覆った。
私は、何をしている。自分に問い詰めたい。彼女はきっと泣いている。なのになんだって泣かないでとすら伝えられない。
赤い血はみるみる流れ出していく。痛みは麻痺してきた。きっとこんなものより彼女はもっとずっと痛いんだ。
まどつきさんは顔を上げて流れ出す血をぼうっと見つめ、小さく呟いた。
「…ごめんね、せんせい」
彼女は包丁を私の胸から抜く。赤い血が飛び散って目にかかる、その狭い視界の隙間に見えた包丁の切っ先の向く方、は。
だめ。
貴方の涙さえも嫌なのに、血なんて、まさか。
彼女の心臓に向けられた包丁をつかむ。
手の痛みなんて気にしていられるか。
体を起こし、唖然とする彼女を見つめ。
そうして、私は。
(包丁があるからと彼女を抱きしめられなかった今までの私は、なんて愚かだったのだろう)
それこそ消えそうな、か細い声で彼女は言う。だらんと下げられた手には力なく包丁が握られ、それは鈍く剣呑な光を放っている。
君こそ、どうしたの。
私は問う。果たして、この声は彼女に届いているんだろうか。
「せんせぇ」
舌っ足らずの甘い声。
振り向くと、部屋の入り口に少女がちょこんと立っていた。いつものとおり両目をつむっていて、どうやって前を見ているのだろうかと不思議に思う。私が言えたことではないけれど。
「まーた来ましたよぅ」
いかにも、無邪気といったふうにまどつきさんは笑う。いらっしゃいと言う前に私はぎょっとして飛び退いた。
きらきら笑う彼女の両手には、なんていうことだ、赤黒く錆びた包丁が握られていたのだ。
あれは痛い。刺されるとこの世の物ではないというぐらいに痛い。身を持って痛感した私が言うのだから間違いない。
私は首を振ってそれは嫌だと示したのに、まどつきさんは包丁をしまうどころか突きつけてきた。彼女は楽しんでいる。間違いない。
「なんで逃げるんですかぁ」
きゃっきゃっとはしゃぐ彼女は必死な私を追いかけてくる。なんでなんて分かっているくせに、分かっているくせに!
どん、後ろから強く押され私は地面に突っ伏してしまう。こんな少女に、情けないとも思うが今はそんなことを嘆く暇は無い。
彼女は私の上にぽすんと座り、包丁の切っ先を私の心の臓にそっと当てる。
ああ、もう駄目だ、捕まってしまった。
刺される。覚悟して、目を固く閉じ冷たい痛みを待った。しかし、いつまで待っても痛みはやってこない。不審に思いながら、私はそっと目を開けた。
下から見上げた彼女は、先程の楽しそうな様子が嘘のように表情を消していた。
「傷、消えたのね」
小さく彼女は呟く。恐らく、彼女がこの前私を刺した傷のことだろう。先生、知ってた? まどつきさんは私に問う。
「ねぇ、わたしね、先生のこと殺してしまいたいって思ってるよ」
先生を刺すのは簡単すぎてつまらないと彼女は笑んだ。
「でも先生、先生は死なないでしょう。心臓を刺したって、どこを何度刺したって。だから私、どうしようもないのだわ」
顔をくしゃりと歪めて言い放つ。その表情がなんだかとても辛そうで、どこか痛いのだろうかと心配になった。見たところ怪我なんかはしておらず、けれど表情は苦しそうだ。どうしたらよいか分からず、とりあえず彼女の頬に手を添える。
まどつきさんは思わずといったふうに両目を開いた。
頬が微かに震えている。彼女の持ち上げられていた両手が両脇に下がる。
「…どうして」
俯いた彼女から、声がこぼれておちた。泣いているのかと、思う。
「あなた、どうして消えないの」
それこそ消えそうな、か細い声で彼女は言う。
君こそ、どうしたの。
私は問う。まどつきさんは黙って首を横に振った。
果たして、届いたのだろうか。
「どうして、どうして、先生は消えてくれないの。わたし、いらないのよ、先生なんか」
どうして、なんで。彼女はそればかり繰り返す。
「いらない、いらない、いらない!!」
突如、強烈な痛みが走って私は呻いた。まどつきさんが包丁を私の胸に突き立てたからだった。じわり、血がにじむ。
「いらないの」
ぽたり、なにか、冷たいものが降ってきた。もどかしいことに、目が霞んで彼女の顔がよく見えない。
ぐるぐる、世界はまわる。その中で、まどつきさんの声だけがいやにはっきり聞こえていた。
「私に優しい人なんていらないわ」
だって、どうせ嘘なんでしょう。
だって、どうせ裏切るんでしょう。
だから先生は嫌いなひとだ。先生は、わたしにとっていらないひとだ。
いらないひと、なのに、どうして?
「どうして、わたしの夢にいてくれるの」
あなたなんかがいてくれたら、泣きたくなってしまうじゃないか。
そう言って、彼女は両手で顔を覆った。
私は、何をしている。自分に問い詰めたい。彼女はきっと泣いている。なのになんだって泣かないでとすら伝えられない。
赤い血はみるみる流れ出していく。痛みは麻痺してきた。きっとこんなものより彼女はもっとずっと痛いんだ。
まどつきさんは顔を上げて流れ出す血をぼうっと見つめ、小さく呟いた。
「…ごめんね、せんせい」
彼女は包丁を私の胸から抜く。赤い血が飛び散って目にかかる、その狭い視界の隙間に見えた包丁の切っ先の向く方、は。
だめ。
貴方の涙さえも嫌なのに、血なんて、まさか。
彼女の心臓に向けられた包丁をつかむ。
手の痛みなんて気にしていられるか。
体を起こし、唖然とする彼女を見つめ。
そうして、私は。
(包丁があるからと彼女を抱きしめられなかった今までの私は、なんて愚かだったのだろう)