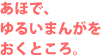
あげない
わたしの愛しい愛しい王子様。
わたしは貴方に大変感謝しているのです。なんて言ったって、貴方のおかげでわたしは生き返ることが出来たんですもの! それについては貴方は不本意だったのかもわかりませんが、それはそれ。
この世で二番目に美しくこの世で一番に忌々しい継母は、焼けた靴で踊り狂って死んでしまいました。お可哀相に、いい様ね。
しかしわたしはふと、思うのです。血のつながりはないにしろ、仮にもあの方とわたしは母と娘。あの心の醜い継母の娘であるわたしが、恋に狂って死んでしまうのは、なんともお似合いではないでしょうか。
「めでたしめでたし」で終わるお話なんてもの、本当はどこにもないのです。Happy Endで終わるお話も、また同様に。
わたしの愛しい愛しい王子様はわたしを彼のお姫様とはしませんでした。彼が愛で慈しむのはすでに死んでしまっている、それ。つまりわたしが生きている限り、彼の王子に愛してもらえることはないのです。なんてどうしようもなく、なんて悲しいことでしょう。
ねえ、もう、こうして息をしていても、なんの意味もありません。きっとこれからも、わたしが愛してほしいと願うのは彼ひとり。しかしそれも、僅かな望みも託すことは出来ないのです。こうして暗い想いを沈ませて、重たい中をずるずると這って生きていくよりは、自ら命を絶ったほうが些か潔いことでしょう。
(もしわたしが死んだとしたら、残るのはわたしの屍。あなたはきっと、泣いて喜んでくれることでしょうね、けれど)
わたしはわたしのことを知っています。わたしの性格が褒められたものではないということも。ねえ、お優しいお姫様であったなら、こんなことは思わなかったのでしょうか。
「あの方ひとり、しあわせになってしまうのは、なんとも憎たらしいことね」
もうどれくらいの時間が経っただろうか、硝子の棺で眠る彼の美しい姫君の死に顔を目にしたあの日から。
一目見て彼女は理想の花嫁だと感じた。それほどまでにあの死に顔は綺麗だった。
しかし彼女は生き返ってしまった。生き返った彼女がやったことは継母への復讐とやら。焼けた靴で踊り狂う貴婦人を見て鮮やかに笑う彼女は壮絶で、それは確かに心を焼くにふさわしいものだったかもしれない。
しかしやはり、彼女は生きた人間であり、その時点で僕にとって理想の花嫁とは言えなかった。一方、彼女にとって僕という存在は身を焦がすに足るものだったらしい。それはほんとうに、哀れなことだとは、思う。
けれど何故だろう。彼女は理想の花嫁などではなかった。だから僕は、また宛ても無く探しに行くのだ。その途方も無い旅の果て、花嫁が見つからなかった後に帰るところを、彼女のいる城と決めているのは。それはどうしてだ。女性のひとり、捨てることは慣れているというのに。
きっと彼女の死に顔が人一倍美しかったからだ。そう思うことにしたけれど、どうにもしっくりこない。彼女がまた死ぬ事を期待でもしているのだろうか。僕はそんなにも、あの死に顔に執着していたのだろうか。
「今帰ったよ、雪白姫」
その声は虚しく響き、返すものはいなかった。この城は元から人が少ない。雪白姫があまり家臣や召使というものを信用していないからだった。あの生い立ちでは仕方の無い事だと思うけれど。
それにしたって静かすぎる。本当に人ひとりいないのではないのだろうか。なにか、あったのだろうか。嫌な予感がする。継母のいない今、彼女に起こりうる脅威と言えば。
「賊の類か…?」
なんと言っても、魔法の鏡が認めるこの世で一番に美しい女性だ。そうでなくても、一国の姫。さらえばいくらでも値がつくに違いない。
自然に足は駆け出していた。もし予感が的中したなら、そう、たとえば、売るにしろ、殺すにしろ、美しい姫君をさらったとして。なにもせずに売るということがあるだろうか。なにもせず、殺すということがあるだろうか。
嫌な汗が伝う感触がした。想像するだけで吐き気がする。彼女が、雪白姫が、まだ清らかなままであってくれと、願う。
ひとつひとつの部屋を見てまわる。人を呼ぶ。名を呼ぶ。名を叫ぶ。数多ある部屋の、けれどどれひとつとして声が返って来はしない。けれどそれでも、探し続ける。息が、きれる。
(どうして)
息を切らして走る僕を、冷静に見つめるどこかの僕。お前はどうしてしまったの?そんな、生きている人間なんかに必死になって。僕は答える。わからない、わからないけど、どうしようもなく、嫌なんだ。
「いなくなって、しまうのが」
息があがってしまい、立ち止まる。ふと窓を覗くと、そこから見えたのは不気味なまでに赤くて大きな炎。それから―…
「ゆきしろ、ひめ」
決めてから、まず最初に行ったのは使用人の皆に解雇を言い渡すこと。主の無い城に使用人だけいたところで何になるというのでしょう。もちろん、十分なお金は持たせましたとも。わたしの勝手で解雇を言い渡され、その上生活に困ってなんかしまったらそれはそれはかわいそうだもの。
使用人の最後の仕事として、火を焚かせました。大きな、もうそれこそ人ひとり包み込むなど容易なぐらいに、大きな火を。小さな火では意味が無いのです。仮にそれで命を落としたとして、けれどそれでは駄目。それならば、こんなことをすることはないのですから。
火を焚かせた使用人もいなくなり、ひとりになって炎を見つめると不思議な心地がしました。この火がわたしを殺すのです。そう思うと燃え盛る火の中に継母の姿を見た気がして、首を振ってその幻覚を払い除けました。同じところにいくのでしょうか、あの継母と、わたしは。それはどうにも気に食わないけれどその罪はきっと同じようなものだから、仕方ないとも思うのです。
「未練がないわけではないわ」
小さく呟く。
「空は澄んでいる。林檎は美味しい。歌は美しい。世界は綺麗。一度死んだからこそ思うのよ。この世界は、泣きたくなるぐらいに綺麗だって。小人さんとのおしゃべりだって楽しいの。城の皆だって愛してくれている。わたしが信じることが出来なくて、ほんとうに悲しいし申し訳ないけれど、わたしは確かに愛されていた。…それに、死んでしまえば、あの方の顔を見ることも声を聞くことも叶わなくなってしまうもの、ね。けれど、どうしようもないの。…どうしようもないのだわ」
自己満足、どこまでも。あの方が悪いのでは、決してない。誰も悪くなんてない。ひとり、いるとすればそれは紛れも無く、わたしのこと。
一歩、足を踏み出す。むせかえるような熱気は拒んでくれているようで。けれど、躊躇はしない。熱気にはためらいを持たなかった。だからわたしの足を止めさせたのは、わたしを呼ぶ声。
ねえ、どうして、いまになって。きてくれたりなんか、してしまったの?
「雪白姫!!」
叫ぶようにして名を呼んだ。見間違いでなければ、あの小さな背は、あの大きな火に身をのりだそうとしてはいなかったか。
彼女が振り返る。黒い瞳を大きく見開いていた。そうしてくしゃり、顔を泣きそうに歪ませる。なにかを言っているようだが、その声は微かでこちらの耳にまでは届かない。
「ねえ、姫。そこは火に近くて危ないよ。離れたほうがいい、その体が焼けてしまう」
彼女が驚かないように、驚いて誤ってその身を火に投じたりなどしないように、なるべく優しく声をかける。
けれど彼女は淡く笑って首を横に振るだけだった。火から、離れようとはしない。
「姫、ひめ、雪白姫、お願いだ、火から離れてくれ」
懇願すると、美しい声が返ってきた。
「そうね、」
彼女がにこり、笑う。その笑みは継母が踊り狂う姿を見ているときのものを彷彿とさせた。ねえ、君、今度は誰を焼こうとしてるの。
「そうね、わたしが焼けてしまったら困るのかしら、王子様は」
さぞ困る事でしょうね、可笑しそうに彼女は言った。
その言葉に込められた自傷的な響きに声が詰まる。
「どうせ死ぬなら、綺麗なままで死んでほしいのでしょう? 死んでいるわたしは確かに貴方様の理想の花嫁だったのでしょう。その御方がいなくなってしまうのは困るものね。わたしは殺すのよ。道連れにするの。貴方の理想の花嫁もろともね」
毒々しく鮮やかに、艶やかに、微笑む。
「なにひとつ、貴方に残してなんかあげやしないわ!」
彼女は両腕を目一杯に広げてみせる。けれどそれでも彼女はあまりにも小さかった。小さくて、細くて、すぐに消えてしまいそうで。
だから、嫌なんだ。生きている人間なんてものは非常に面倒だ。そして大変に気持ち悪い。気に入らないことがあれば愚痴や文句を言い、それがこうやって行動に移せばこれほど性質の悪いものはない。手を握れば暖かく、血管が脈を打つ。声をかければ表情をみせる。眉を寄せて怒る。涙を流して悲しむ。頬を持ち上げて笑う。気持ち悪い、気持ち悪い! だって、そうだ、いずれは冷えて固まってしまう。それがどんなに暖かくても、それがどんなに優しくても、それをどんなに愛しく思っていたとしても!
どうせ無くなってしまうなら、最初から存在しないほうが、ずっといい。
何も残さない、彼女は言う。彼女にしては小さな意地悪なのだろうか。どうせ死んでしまうのだから、どうせなら、と。彼女は分かっていない。僕は分かってしまった。分かりたくなんてなかった、のに。
わかってしまったんだ、彼女がいなくなってしまったら、彼女の死体なんてあってもなくても同じように無意味なものだということを。
「どうしたら、いい?」
問い掛けると、彼女は愉快そうに「何を?」と聞き返す。
「君はどうしたら死ぬのをやめてくれる?」
「まあ、可笑しなことをおっしゃるのね」
「至って本気だよ」
「…馬鹿なことを言わないで。それではどうしてほしいというの? どうやって死んでほしいのかしら? やはり毒がいいのでしょうね、傷が無くて綺麗ですもの。けれどお生憎様、なんにもあげないと言ったでしょう?」
「そうじゃない」
「では、なに?」
「…死ぬこと、それ自体をやめてほしいと。そう頼んでいる」
「……はあ?」
彼女の美しい顔がひきつる。僕を見るその目は、なにか信じられないものを見るそれ。ゆっくりと、まばたきをした。顔を歪ませ、そしてゆるく、首を振る。
「…嘘がお上手ね、優しい貴方」
囁くように彼女は言った。消えそうなまでに弱々しい声だった。
きっと彼女は信じてくれない。身から出た錆。しかしなんだってどうにか信じてもらわないといけない。それならば彼女の言うように、嘘が上手になるべきか。
僕が一歩踏み出すと、彼女は警戒するように睨みつけてきた。
「信じてくれなくてもいい。そう、君の言うように、君の死体がなくなったら困るっていうその理由だってなんだって構わない。なんでもいいよ、なんでもいいから、その火に飛び込むこと、それだけは止めてくれ」
「…いやよ。近くに、こないで。もう決めたの、決めたんだから…」
怯えたように声を震わせ、彼女は一歩後退する。火に近づく。背筋が冷える感覚。止めるために、高らかに声をあげた。
「それじゃあこうしよう」
俯いていた彼女が顔を持ち上げる。
「もう止めはしない。飛び込んでくれていい。だがその代わり、僕も一緒だ」
「いっしょ? なにを、いって、」
「言葉通りだよ」
また一歩、彼女に近づく。彼女は後退しない。そのことに心の内で安堵して、けれどゆっくり、彼女に歩み寄っていく。彼女はただ、うろたえている。
「こないで、こないで!! あなた、頭がおかしいわ! こないでったら!! これ以上、近づいたら、そう、飛び込んでやる!」
「それじゃあ、そのあとを僕が追いかけるよ」
「っ、やめてよ! わたしはひとりで死ぬの! 誰かと共に死ぬなんて絶対に嫌! なあに、可哀相だとでも思ったの!? それとも花嫁探しに疲れでもした!? どうだっていいけどね、わたしを都合良く使わないで頂戴!!」
黒耀の髪を振り乱して彼女は悲鳴を上げるように叫んだ。瞳に光るものはきっと涙だ。
僕が死ぬ理由なんてひとつもなかった。その気も無かった。ただの詭弁だった。でもこのくだらない詭弁を、彼女が軽く一蹴する事など出来ないと僕は知っていた。
彼女は、愚かなまでにやさしいひとだから。
彼女の前に立つ。差し伸べた手を、彼女は忌々しそうに見つめてきた。
「…あなたは、ずるい」
「そうだね」
「だって、わたし、あなたのこと好きなのよ」
「うん」
「あなたそれを知ってるのね。知っていて、一緒に、なんて、ひどい。ひどいよ」
「…うん」
「ひどいよ、わたしができないって、わかってて、なのに、なのに」
「…ごめんね」
彼女は目に涙を溜め、いくらかの迷いのあと僕の手にそろりと触れる、その瞬間。
「!!」
ぐいと、腕をつかんで強引に引き寄せる。小さな彼女はいともたやすく腕の中に納まってしまった。
強く抱きしめ、苦しそうにもがく彼女に構わず、安堵のため息をつく。
「良かった」
ひとつ呟くと、雪白姫は不審げに顔をしかめた。不服そうに皮肉を言う。
「骨だけの死体にならなくて良かったことね」
僕は苦く笑う。確かになんと言っても僕は僕だから、やはり生きている人間より死体のほうが、遥かに素敵だとは、思う。けれどきっと、彼女がその「素敵」である必要はないんだ。
一応の危機は回避した。しかしこれで解決したわけではない。彼女はまだ、露ほども僕を信用してはいない。
これからだ、と思う。信用してもらうのも、そこからはじまるものも、すべて、これから。
声が聞こえる。雪白姫を呼ぶ声だ。あれは確か、雪白姫のじいやとやらだったっけ。それだけじゃない、城の使用人たちが何人も。
雪白姫は呆然と声のしたほうを見て、そうして顔を歪ませ、なんでかえってきたの、なんて呟いた。そんなのきっと、僕と同じような理由だろう。
「君は君が思うより愛されているんだよ。皆とか、僕とかにね」
そんな格好良いことを言う僕を軽蔑の視線で一瞥し、彼女は使用人たちの元へかけていった。
うん、なかなか、難しいかもわからない。
わたしは貴方に大変感謝しているのです。なんて言ったって、貴方のおかげでわたしは生き返ることが出来たんですもの! それについては貴方は不本意だったのかもわかりませんが、それはそれ。
この世で二番目に美しくこの世で一番に忌々しい継母は、焼けた靴で踊り狂って死んでしまいました。お可哀相に、いい様ね。
しかしわたしはふと、思うのです。血のつながりはないにしろ、仮にもあの方とわたしは母と娘。あの心の醜い継母の娘であるわたしが、恋に狂って死んでしまうのは、なんともお似合いではないでしょうか。
「めでたしめでたし」で終わるお話なんてもの、本当はどこにもないのです。Happy Endで終わるお話も、また同様に。
わたしの愛しい愛しい王子様はわたしを彼のお姫様とはしませんでした。彼が愛で慈しむのはすでに死んでしまっている、それ。つまりわたしが生きている限り、彼の王子に愛してもらえることはないのです。なんてどうしようもなく、なんて悲しいことでしょう。
ねえ、もう、こうして息をしていても、なんの意味もありません。きっとこれからも、わたしが愛してほしいと願うのは彼ひとり。しかしそれも、僅かな望みも託すことは出来ないのです。こうして暗い想いを沈ませて、重たい中をずるずると這って生きていくよりは、自ら命を絶ったほうが些か潔いことでしょう。
(もしわたしが死んだとしたら、残るのはわたしの屍。あなたはきっと、泣いて喜んでくれることでしょうね、けれど)
わたしはわたしのことを知っています。わたしの性格が褒められたものではないということも。ねえ、お優しいお姫様であったなら、こんなことは思わなかったのでしょうか。
「あの方ひとり、しあわせになってしまうのは、なんとも憎たらしいことね」
もうどれくらいの時間が経っただろうか、硝子の棺で眠る彼の美しい姫君の死に顔を目にしたあの日から。
一目見て彼女は理想の花嫁だと感じた。それほどまでにあの死に顔は綺麗だった。
しかし彼女は生き返ってしまった。生き返った彼女がやったことは継母への復讐とやら。焼けた靴で踊り狂う貴婦人を見て鮮やかに笑う彼女は壮絶で、それは確かに心を焼くにふさわしいものだったかもしれない。
しかしやはり、彼女は生きた人間であり、その時点で僕にとって理想の花嫁とは言えなかった。一方、彼女にとって僕という存在は身を焦がすに足るものだったらしい。それはほんとうに、哀れなことだとは、思う。
けれど何故だろう。彼女は理想の花嫁などではなかった。だから僕は、また宛ても無く探しに行くのだ。その途方も無い旅の果て、花嫁が見つからなかった後に帰るところを、彼女のいる城と決めているのは。それはどうしてだ。女性のひとり、捨てることは慣れているというのに。
きっと彼女の死に顔が人一倍美しかったからだ。そう思うことにしたけれど、どうにもしっくりこない。彼女がまた死ぬ事を期待でもしているのだろうか。僕はそんなにも、あの死に顔に執着していたのだろうか。
「今帰ったよ、雪白姫」
その声は虚しく響き、返すものはいなかった。この城は元から人が少ない。雪白姫があまり家臣や召使というものを信用していないからだった。あの生い立ちでは仕方の無い事だと思うけれど。
それにしたって静かすぎる。本当に人ひとりいないのではないのだろうか。なにか、あったのだろうか。嫌な予感がする。継母のいない今、彼女に起こりうる脅威と言えば。
「賊の類か…?」
なんと言っても、魔法の鏡が認めるこの世で一番に美しい女性だ。そうでなくても、一国の姫。さらえばいくらでも値がつくに違いない。
自然に足は駆け出していた。もし予感が的中したなら、そう、たとえば、売るにしろ、殺すにしろ、美しい姫君をさらったとして。なにもせずに売るということがあるだろうか。なにもせず、殺すということがあるだろうか。
嫌な汗が伝う感触がした。想像するだけで吐き気がする。彼女が、雪白姫が、まだ清らかなままであってくれと、願う。
ひとつひとつの部屋を見てまわる。人を呼ぶ。名を呼ぶ。名を叫ぶ。数多ある部屋の、けれどどれひとつとして声が返って来はしない。けれどそれでも、探し続ける。息が、きれる。
(どうして)
息を切らして走る僕を、冷静に見つめるどこかの僕。お前はどうしてしまったの?そんな、生きている人間なんかに必死になって。僕は答える。わからない、わからないけど、どうしようもなく、嫌なんだ。
「いなくなって、しまうのが」
息があがってしまい、立ち止まる。ふと窓を覗くと、そこから見えたのは不気味なまでに赤くて大きな炎。それから―…
「ゆきしろ、ひめ」
決めてから、まず最初に行ったのは使用人の皆に解雇を言い渡すこと。主の無い城に使用人だけいたところで何になるというのでしょう。もちろん、十分なお金は持たせましたとも。わたしの勝手で解雇を言い渡され、その上生活に困ってなんかしまったらそれはそれはかわいそうだもの。
使用人の最後の仕事として、火を焚かせました。大きな、もうそれこそ人ひとり包み込むなど容易なぐらいに、大きな火を。小さな火では意味が無いのです。仮にそれで命を落としたとして、けれどそれでは駄目。それならば、こんなことをすることはないのですから。
火を焚かせた使用人もいなくなり、ひとりになって炎を見つめると不思議な心地がしました。この火がわたしを殺すのです。そう思うと燃え盛る火の中に継母の姿を見た気がして、首を振ってその幻覚を払い除けました。同じところにいくのでしょうか、あの継母と、わたしは。それはどうにも気に食わないけれどその罪はきっと同じようなものだから、仕方ないとも思うのです。
「未練がないわけではないわ」
小さく呟く。
「空は澄んでいる。林檎は美味しい。歌は美しい。世界は綺麗。一度死んだからこそ思うのよ。この世界は、泣きたくなるぐらいに綺麗だって。小人さんとのおしゃべりだって楽しいの。城の皆だって愛してくれている。わたしが信じることが出来なくて、ほんとうに悲しいし申し訳ないけれど、わたしは確かに愛されていた。…それに、死んでしまえば、あの方の顔を見ることも声を聞くことも叶わなくなってしまうもの、ね。けれど、どうしようもないの。…どうしようもないのだわ」
自己満足、どこまでも。あの方が悪いのでは、決してない。誰も悪くなんてない。ひとり、いるとすればそれは紛れも無く、わたしのこと。
一歩、足を踏み出す。むせかえるような熱気は拒んでくれているようで。けれど、躊躇はしない。熱気にはためらいを持たなかった。だからわたしの足を止めさせたのは、わたしを呼ぶ声。
ねえ、どうして、いまになって。きてくれたりなんか、してしまったの?
「雪白姫!!」
叫ぶようにして名を呼んだ。見間違いでなければ、あの小さな背は、あの大きな火に身をのりだそうとしてはいなかったか。
彼女が振り返る。黒い瞳を大きく見開いていた。そうしてくしゃり、顔を泣きそうに歪ませる。なにかを言っているようだが、その声は微かでこちらの耳にまでは届かない。
「ねえ、姫。そこは火に近くて危ないよ。離れたほうがいい、その体が焼けてしまう」
彼女が驚かないように、驚いて誤ってその身を火に投じたりなどしないように、なるべく優しく声をかける。
けれど彼女は淡く笑って首を横に振るだけだった。火から、離れようとはしない。
「姫、ひめ、雪白姫、お願いだ、火から離れてくれ」
懇願すると、美しい声が返ってきた。
「そうね、」
彼女がにこり、笑う。その笑みは継母が踊り狂う姿を見ているときのものを彷彿とさせた。ねえ、君、今度は誰を焼こうとしてるの。
「そうね、わたしが焼けてしまったら困るのかしら、王子様は」
さぞ困る事でしょうね、可笑しそうに彼女は言った。
その言葉に込められた自傷的な響きに声が詰まる。
「どうせ死ぬなら、綺麗なままで死んでほしいのでしょう? 死んでいるわたしは確かに貴方様の理想の花嫁だったのでしょう。その御方がいなくなってしまうのは困るものね。わたしは殺すのよ。道連れにするの。貴方の理想の花嫁もろともね」
毒々しく鮮やかに、艶やかに、微笑む。
「なにひとつ、貴方に残してなんかあげやしないわ!」
彼女は両腕を目一杯に広げてみせる。けれどそれでも彼女はあまりにも小さかった。小さくて、細くて、すぐに消えてしまいそうで。
だから、嫌なんだ。生きている人間なんてものは非常に面倒だ。そして大変に気持ち悪い。気に入らないことがあれば愚痴や文句を言い、それがこうやって行動に移せばこれほど性質の悪いものはない。手を握れば暖かく、血管が脈を打つ。声をかければ表情をみせる。眉を寄せて怒る。涙を流して悲しむ。頬を持ち上げて笑う。気持ち悪い、気持ち悪い! だって、そうだ、いずれは冷えて固まってしまう。それがどんなに暖かくても、それがどんなに優しくても、それをどんなに愛しく思っていたとしても!
どうせ無くなってしまうなら、最初から存在しないほうが、ずっといい。
何も残さない、彼女は言う。彼女にしては小さな意地悪なのだろうか。どうせ死んでしまうのだから、どうせなら、と。彼女は分かっていない。僕は分かってしまった。分かりたくなんてなかった、のに。
わかってしまったんだ、彼女がいなくなってしまったら、彼女の死体なんてあってもなくても同じように無意味なものだということを。
「どうしたら、いい?」
問い掛けると、彼女は愉快そうに「何を?」と聞き返す。
「君はどうしたら死ぬのをやめてくれる?」
「まあ、可笑しなことをおっしゃるのね」
「至って本気だよ」
「…馬鹿なことを言わないで。それではどうしてほしいというの? どうやって死んでほしいのかしら? やはり毒がいいのでしょうね、傷が無くて綺麗ですもの。けれどお生憎様、なんにもあげないと言ったでしょう?」
「そうじゃない」
「では、なに?」
「…死ぬこと、それ自体をやめてほしいと。そう頼んでいる」
「……はあ?」
彼女の美しい顔がひきつる。僕を見るその目は、なにか信じられないものを見るそれ。ゆっくりと、まばたきをした。顔を歪ませ、そしてゆるく、首を振る。
「…嘘がお上手ね、優しい貴方」
囁くように彼女は言った。消えそうなまでに弱々しい声だった。
きっと彼女は信じてくれない。身から出た錆。しかしなんだってどうにか信じてもらわないといけない。それならば彼女の言うように、嘘が上手になるべきか。
僕が一歩踏み出すと、彼女は警戒するように睨みつけてきた。
「信じてくれなくてもいい。そう、君の言うように、君の死体がなくなったら困るっていうその理由だってなんだって構わない。なんでもいいよ、なんでもいいから、その火に飛び込むこと、それだけは止めてくれ」
「…いやよ。近くに、こないで。もう決めたの、決めたんだから…」
怯えたように声を震わせ、彼女は一歩後退する。火に近づく。背筋が冷える感覚。止めるために、高らかに声をあげた。
「それじゃあこうしよう」
俯いていた彼女が顔を持ち上げる。
「もう止めはしない。飛び込んでくれていい。だがその代わり、僕も一緒だ」
「いっしょ? なにを、いって、」
「言葉通りだよ」
また一歩、彼女に近づく。彼女は後退しない。そのことに心の内で安堵して、けれどゆっくり、彼女に歩み寄っていく。彼女はただ、うろたえている。
「こないで、こないで!! あなた、頭がおかしいわ! こないでったら!! これ以上、近づいたら、そう、飛び込んでやる!」
「それじゃあ、そのあとを僕が追いかけるよ」
「っ、やめてよ! わたしはひとりで死ぬの! 誰かと共に死ぬなんて絶対に嫌! なあに、可哀相だとでも思ったの!? それとも花嫁探しに疲れでもした!? どうだっていいけどね、わたしを都合良く使わないで頂戴!!」
黒耀の髪を振り乱して彼女は悲鳴を上げるように叫んだ。瞳に光るものはきっと涙だ。
僕が死ぬ理由なんてひとつもなかった。その気も無かった。ただの詭弁だった。でもこのくだらない詭弁を、彼女が軽く一蹴する事など出来ないと僕は知っていた。
彼女は、愚かなまでにやさしいひとだから。
彼女の前に立つ。差し伸べた手を、彼女は忌々しそうに見つめてきた。
「…あなたは、ずるい」
「そうだね」
「だって、わたし、あなたのこと好きなのよ」
「うん」
「あなたそれを知ってるのね。知っていて、一緒に、なんて、ひどい。ひどいよ」
「…うん」
「ひどいよ、わたしができないって、わかってて、なのに、なのに」
「…ごめんね」
彼女は目に涙を溜め、いくらかの迷いのあと僕の手にそろりと触れる、その瞬間。
「!!」
ぐいと、腕をつかんで強引に引き寄せる。小さな彼女はいともたやすく腕の中に納まってしまった。
強く抱きしめ、苦しそうにもがく彼女に構わず、安堵のため息をつく。
「良かった」
ひとつ呟くと、雪白姫は不審げに顔をしかめた。不服そうに皮肉を言う。
「骨だけの死体にならなくて良かったことね」
僕は苦く笑う。確かになんと言っても僕は僕だから、やはり生きている人間より死体のほうが、遥かに素敵だとは、思う。けれどきっと、彼女がその「素敵」である必要はないんだ。
一応の危機は回避した。しかしこれで解決したわけではない。彼女はまだ、露ほども僕を信用してはいない。
これからだ、と思う。信用してもらうのも、そこからはじまるものも、すべて、これから。
声が聞こえる。雪白姫を呼ぶ声だ。あれは確か、雪白姫のじいやとやらだったっけ。それだけじゃない、城の使用人たちが何人も。
雪白姫は呆然と声のしたほうを見て、そうして顔を歪ませ、なんでかえってきたの、なんて呟いた。そんなのきっと、僕と同じような理由だろう。
「君は君が思うより愛されているんだよ。皆とか、僕とかにね」
そんな格好良いことを言う僕を軽蔑の視線で一瞥し、彼女は使用人たちの元へかけていった。
うん、なかなか、難しいかもわからない。