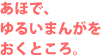
それはちがうの
ねえ、分かってるよ。
君がとにかくポケモンが大好きで大切でラブだってこと、もうとっくに聞き飽きてしまったよ。
だからね、お願い。
ポケモンをラブだと言うその口で、わたしのことを好きだなんて言わないで。
「好きだよ」
君は無邪気に笑う。無邪気だからこそ、タチが悪いのはなおのこと。
「人間のことを、こんなに好きになるなんて。今までの僕じゃあ考えられない」
君の言葉は甘い。甘くて心地よくて、すぅと溶け込んでくる。
わたしには、それが不快で不快で仕方ないのだけれど。
顔を歪めて笑ってみせた。さぞ意地悪そうな笑みになっていることだろう。そうなっていてほしい。
「そうなの、へぇ。それは良かったね」
君の顔から笑みが引く。ざまあみろ、ざまーみろ。
「でも、わたしは君のこと、大嫌いだよ」
吐き気がしそうなくらい大嫌い。
微笑んで言いのけ、目をそらす。君はどうせ、悲しそうな顔をして、なんで、なんて聞くんだ。
なんで、なんてねえ。わたしがわたしに聞きたいよ。言ってしまえばいいのに。ああ、でも、悔しいじゃないか。 言ってしまって、それで馬鹿になるのは、わたしだ。
だから言わないと決めたんだ。一生何があっても言ってやんない。君なんか、わたしのこと、嫌いになってしまえばいい。
人を好きになれて良かったね。おめでとう。それならそう、さっさと他の人を好きになってしまってよ。
「僕は、」
沈黙の後、君は口を開く。その表情を盗み見て、わたしは微かに驚いた。てっきり、母親に置いてかれた子供みたいな、そんな目をしてるんだろうと思っていた。なのに、君の瞳はゆらぐこともなく、静かだった。
「僕は、君が好きでいてくれなくても、君が好きだよ」
ゆらゆら、ゆらぐ。震えてしまう。だめ、だめ。決めたんだ。言わないと、ゆらがないと、決めたんだ。
「きらい、」
零れた言葉は情けないほどに震えてた。
冗談じゃない、冗談じゃない!
「わたしが、きらいだって、いってるの! きえて、いなくなって!!」
子供が駄々をこねるみたいに叫んだ。泣きたかった。死んでしまいたい。
君は目を細め、手を伸ばしてくる。振り払わなければ、振り払わ、ないと。
「やめて」
かすれる声で、制止した。
「さわらないで」
だって、そう、馬鹿。馬鹿だよ、だって君は、わたしのことなんて好きじゃない。君は履き違えている。君のそれは、恋愛感情じゃあない。
君はポケモンが大切で、それとおんなじ。それ以上になんてなりっこない。
君がそうだってのに、悔しいじゃないか。わたしだけ、恋してるだなんて。
君のそれが恋ではない「好き」だというのに、わたしだけ君に恋して「好き」と囁くなんて馬鹿みたい。
こんな恋、そんな形で実るよりはね、君がわたしを嫌いになって壊れてしまったほうが、きっといい。
「わたしじゃなくてもいいでしょう」
ぽつり、こぼす。
「今はまだ駄目でも、君は本当に人間みたいだから、いつか恋することが出来てしまうよ。わたしじゃない、他の人に、恋できるわ、きっと」
君は目を見開く。君は気づいていないんだ。
「きみ、きみ、わたしに恋してなんて、いないのよ」
はっきりと声にすると、どこかがズキリと痛んだ。わかりきった、ことなのに。形にするだけで、声にするだけで、こんなに痛いだなんて。
君は顔を歪めた。わたしに負けないぐらいに痛そうだった。なんで?なんで君がそんな顔をするの。
「君は僕を相当に馬鹿にしている」
してるよ、だって、そう。そうじゃない、そうでなかったら、こんなに苦しくなんてない!
わたしが何も言い返せず、ただ突っ立っていると、君は一歩わたしに歩み寄る。
視線が、絡まる。
「僕が、恋と、そうでないものの判別ぐらいつかないとでも、思ってるの」
意地悪すぎはしないか、と君は吐き捨てる。
「大嫌いって、他の人を好きになれって、あげくの果てに、僕が君を好きじゃない?ふざけないでくれる?」
ただ呆然と君を見る。君は忌々しそうに、睨みつけてくる。
「言っただろう、君が僕を好きじゃくても僕は君が好きだって」
そんなはずはない。だって、君は、君が好きなのは、ポケモンで、わたしは、それと、おなじでー…、
「君はどうせ、僕なんて好きじゃないんだろ。だからといって、ひどすぎるよ」
君の声が零れる。泣いてしまう、と、思った。
なにも言えなかった。黙っていると、君の手が頬に触れてきた。振り払うことは、出来なかった。
「…N」
名前を呼んだ。聞こえたかどうかは分からない。それでも君は、目を細め。
「好きだよ、トウコ」
顔が、近づいた。
君がとにかくポケモンが大好きで大切でラブだってこと、もうとっくに聞き飽きてしまったよ。
だからね、お願い。
ポケモンをラブだと言うその口で、わたしのことを好きだなんて言わないで。
「好きだよ」
君は無邪気に笑う。無邪気だからこそ、タチが悪いのはなおのこと。
「人間のことを、こんなに好きになるなんて。今までの僕じゃあ考えられない」
君の言葉は甘い。甘くて心地よくて、すぅと溶け込んでくる。
わたしには、それが不快で不快で仕方ないのだけれど。
顔を歪めて笑ってみせた。さぞ意地悪そうな笑みになっていることだろう。そうなっていてほしい。
「そうなの、へぇ。それは良かったね」
君の顔から笑みが引く。ざまあみろ、ざまーみろ。
「でも、わたしは君のこと、大嫌いだよ」
吐き気がしそうなくらい大嫌い。
微笑んで言いのけ、目をそらす。君はどうせ、悲しそうな顔をして、なんで、なんて聞くんだ。
なんで、なんてねえ。わたしがわたしに聞きたいよ。言ってしまえばいいのに。ああ、でも、悔しいじゃないか。 言ってしまって、それで馬鹿になるのは、わたしだ。
だから言わないと決めたんだ。一生何があっても言ってやんない。君なんか、わたしのこと、嫌いになってしまえばいい。
人を好きになれて良かったね。おめでとう。それならそう、さっさと他の人を好きになってしまってよ。
「僕は、」
沈黙の後、君は口を開く。その表情を盗み見て、わたしは微かに驚いた。てっきり、母親に置いてかれた子供みたいな、そんな目をしてるんだろうと思っていた。なのに、君の瞳はゆらぐこともなく、静かだった。
「僕は、君が好きでいてくれなくても、君が好きだよ」
ゆらゆら、ゆらぐ。震えてしまう。だめ、だめ。決めたんだ。言わないと、ゆらがないと、決めたんだ。
「きらい、」
零れた言葉は情けないほどに震えてた。
冗談じゃない、冗談じゃない!
「わたしが、きらいだって、いってるの! きえて、いなくなって!!」
子供が駄々をこねるみたいに叫んだ。泣きたかった。死んでしまいたい。
君は目を細め、手を伸ばしてくる。振り払わなければ、振り払わ、ないと。
「やめて」
かすれる声で、制止した。
「さわらないで」
だって、そう、馬鹿。馬鹿だよ、だって君は、わたしのことなんて好きじゃない。君は履き違えている。君のそれは、恋愛感情じゃあない。
君はポケモンが大切で、それとおんなじ。それ以上になんてなりっこない。
君がそうだってのに、悔しいじゃないか。わたしだけ、恋してるだなんて。
君のそれが恋ではない「好き」だというのに、わたしだけ君に恋して「好き」と囁くなんて馬鹿みたい。
こんな恋、そんな形で実るよりはね、君がわたしを嫌いになって壊れてしまったほうが、きっといい。
「わたしじゃなくてもいいでしょう」
ぽつり、こぼす。
「今はまだ駄目でも、君は本当に人間みたいだから、いつか恋することが出来てしまうよ。わたしじゃない、他の人に、恋できるわ、きっと」
君は目を見開く。君は気づいていないんだ。
「きみ、きみ、わたしに恋してなんて、いないのよ」
はっきりと声にすると、どこかがズキリと痛んだ。わかりきった、ことなのに。形にするだけで、声にするだけで、こんなに痛いだなんて。
君は顔を歪めた。わたしに負けないぐらいに痛そうだった。なんで?なんで君がそんな顔をするの。
「君は僕を相当に馬鹿にしている」
してるよ、だって、そう。そうじゃない、そうでなかったら、こんなに苦しくなんてない!
わたしが何も言い返せず、ただ突っ立っていると、君は一歩わたしに歩み寄る。
視線が、絡まる。
「僕が、恋と、そうでないものの判別ぐらいつかないとでも、思ってるの」
意地悪すぎはしないか、と君は吐き捨てる。
「大嫌いって、他の人を好きになれって、あげくの果てに、僕が君を好きじゃない?ふざけないでくれる?」
ただ呆然と君を見る。君は忌々しそうに、睨みつけてくる。
「言っただろう、君が僕を好きじゃくても僕は君が好きだって」
そんなはずはない。だって、君は、君が好きなのは、ポケモンで、わたしは、それと、おなじでー…、
「君はどうせ、僕なんて好きじゃないんだろ。だからといって、ひどすぎるよ」
君の声が零れる。泣いてしまう、と、思った。
なにも言えなかった。黙っていると、君の手が頬に触れてきた。振り払うことは、出来なかった。
「…N」
名前を呼んだ。聞こえたかどうかは分からない。それでも君は、目を細め。
「好きだよ、トウコ」
顔が、近づいた。