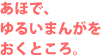
あっかんべぇ
人が物理的要因で死ぬときってさ、たいてい音がするじゃない。大きな音だったり、気持ち悪い音だったりね。
けれど首を絞める殺しかたはどうだろう、音はするのかな。骨の軋む音ぐらいかな。
殺されるほうがうめきごえひとつあげなかったら、静かに死んでいくのかなあ。殺したことも死んだこともないからよく分かんない。
絞殺に思いをはせてはみるものの、なんだか頭がうまく働かない。
それはそう、だって酸素が足りないんだもの。
わたしの首にかけられている両手は生ぬるい温度だった。
その手がわたしの喉を締め付けているせいで、呼吸があんまりうまく出来ない。声を吐いて彼に理由を問うことも出来なかった。問いかける気もないけれど。
霞む意識のなか、彼の顔を見上げると目があった。首を締められているわたしより息の詰まったかんじの顔だ。
「ねぇ、いっしょに死んでしまおうよ」
懇願のような彼のこえ。
「この世界はたいへんに薄情だ。永遠なんて存在しない世界だ。僕が君を好きなのだって、永遠じゃあなくなってしまうかもしれない」
ばかだな、ばかだなあ君は。
心のなかで彼をなじる。彼はたいへんに愚かなひとで、たいへんに怖がりなひとでもあった。
いっしょに死のうと首を絞める彼は、けれどいざ骨の軋む音がしたら首から手を離してしまうのだ。
手を離されたわたしは反射的に息をして生きたままになってしまう。この嘘つきは困ったものだと生理的な涙のにじむ目で彼を見れば、彼は憂いを含んだ涙を存分に流しわたしに謝罪し始めるのだ。
そのパターン化された流れを、何度もなんども繰り返した。そういう性癖なんだろうかと考えもしたけれど、別に興奮するわけでもないらしい。
終わりにしようかと思う。わたしはこの関係のままでも悪くはないと思うけれど、涙を流し謝る彼はみっともなくて可哀想だ。それにもしわたしを殺せたとしても、彼はきっと自分を殺せない。酷いまでの馬鹿だけど、だからわたしは好きになったのだ。
わたしを殺すのを止めさせてあげる。自己陶酔の自業自得の平行線を終わりにしてしまおう。
首にかけられた手にわたしの手を添える。やはりどうにも生ぬるい温度だ。
君は驚いたみたいで、手の力が弱まった。わたしは酸素を吸うのもそこそこに、彼の目を見て言葉を放つ。
「いっしょに死んでどうなるの?」
言葉を鋭くして刃にする。彼の心臓に届けばいいなあ。
「ねえ、きみ、もしかしていっしょに死ねばいっしょのとこに逝けるとでも思った? それはあまりにもひどい間違いじゃあないかな、だってそれが成立するのってさ、相思相愛のふたりでないと無理じゃないの」
君は固まったように動かない。けれど手だけが微かに震えているのがわたしには分かった。そう、そうだよ、きみだって分かるよね、わたしはね。
「馬鹿なきみなんてだぁいきらい」
なんて、真っ赤な嘘だ。
けれど君はこの言葉を信じてくれる。だってほら、手に力がこもってきた。
ねえ、君はこの嘘をずっと疑わないでくれるかな。君はずっと、わたしに嫌われてるって、愛されてなんかなかったって、信じていてくれるかな。ずっとずうっと苦しんでくれるかな?
「あはは、はは、ねえ、わたし、君に殺されるなんて嫌だなぁ。やーだなあ。あは、は」
圧迫されていく喉から声を絞りだした。
うそ、君が殺してくれるんならそれがいい。それがよかった。
「ねえ、ねぇ」
呼びかける。こちらを見つめる暗い瞳に涙は浮かんでおらず、密かに満足する。彼の豊かな心がきらいだった。
先ほどのわたしの言葉の刃で、君の豊かな心を切り裂くことが出来ていたら成功だ。更にわたしが今からすることで修繕不可能になってしまえば大成功だ。
わたしは彼に笑ってみせる。
「ばいばーい」
軽い別れの挨拶のあと、べぇ、と舌をつきだす。
不可解を示す君の顔が、みるみる蒼くなっていくのが可愛い。
そうして、思い切り、わたしは×を×××ったのだ。
わたしの願いはただひとつ。
君の心がわたしの心臓といっしょに死んでくれれば、嬉しいの。
けれど首を絞める殺しかたはどうだろう、音はするのかな。骨の軋む音ぐらいかな。
殺されるほうがうめきごえひとつあげなかったら、静かに死んでいくのかなあ。殺したことも死んだこともないからよく分かんない。
絞殺に思いをはせてはみるものの、なんだか頭がうまく働かない。
それはそう、だって酸素が足りないんだもの。
わたしの首にかけられている両手は生ぬるい温度だった。
その手がわたしの喉を締め付けているせいで、呼吸があんまりうまく出来ない。声を吐いて彼に理由を問うことも出来なかった。問いかける気もないけれど。
霞む意識のなか、彼の顔を見上げると目があった。首を締められているわたしより息の詰まったかんじの顔だ。
「ねぇ、いっしょに死んでしまおうよ」
懇願のような彼のこえ。
「この世界はたいへんに薄情だ。永遠なんて存在しない世界だ。僕が君を好きなのだって、永遠じゃあなくなってしまうかもしれない」
ばかだな、ばかだなあ君は。
心のなかで彼をなじる。彼はたいへんに愚かなひとで、たいへんに怖がりなひとでもあった。
いっしょに死のうと首を絞める彼は、けれどいざ骨の軋む音がしたら首から手を離してしまうのだ。
手を離されたわたしは反射的に息をして生きたままになってしまう。この嘘つきは困ったものだと生理的な涙のにじむ目で彼を見れば、彼は憂いを含んだ涙を存分に流しわたしに謝罪し始めるのだ。
そのパターン化された流れを、何度もなんども繰り返した。そういう性癖なんだろうかと考えもしたけれど、別に興奮するわけでもないらしい。
終わりにしようかと思う。わたしはこの関係のままでも悪くはないと思うけれど、涙を流し謝る彼はみっともなくて可哀想だ。それにもしわたしを殺せたとしても、彼はきっと自分を殺せない。酷いまでの馬鹿だけど、だからわたしは好きになったのだ。
わたしを殺すのを止めさせてあげる。自己陶酔の自業自得の平行線を終わりにしてしまおう。
首にかけられた手にわたしの手を添える。やはりどうにも生ぬるい温度だ。
君は驚いたみたいで、手の力が弱まった。わたしは酸素を吸うのもそこそこに、彼の目を見て言葉を放つ。
「いっしょに死んでどうなるの?」
言葉を鋭くして刃にする。彼の心臓に届けばいいなあ。
「ねえ、きみ、もしかしていっしょに死ねばいっしょのとこに逝けるとでも思った? それはあまりにもひどい間違いじゃあないかな、だってそれが成立するのってさ、相思相愛のふたりでないと無理じゃないの」
君は固まったように動かない。けれど手だけが微かに震えているのがわたしには分かった。そう、そうだよ、きみだって分かるよね、わたしはね。
「馬鹿なきみなんてだぁいきらい」
なんて、真っ赤な嘘だ。
けれど君はこの言葉を信じてくれる。だってほら、手に力がこもってきた。
ねえ、君はこの嘘をずっと疑わないでくれるかな。君はずっと、わたしに嫌われてるって、愛されてなんかなかったって、信じていてくれるかな。ずっとずうっと苦しんでくれるかな?
「あはは、はは、ねえ、わたし、君に殺されるなんて嫌だなぁ。やーだなあ。あは、は」
圧迫されていく喉から声を絞りだした。
うそ、君が殺してくれるんならそれがいい。それがよかった。
「ねえ、ねぇ」
呼びかける。こちらを見つめる暗い瞳に涙は浮かんでおらず、密かに満足する。彼の豊かな心がきらいだった。
先ほどのわたしの言葉の刃で、君の豊かな心を切り裂くことが出来ていたら成功だ。更にわたしが今からすることで修繕不可能になってしまえば大成功だ。
わたしは彼に笑ってみせる。
「ばいばーい」
軽い別れの挨拶のあと、べぇ、と舌をつきだす。
不可解を示す君の顔が、みるみる蒼くなっていくのが可愛い。
そうして、思い切り、わたしは×を×××ったのだ。
わたしの願いはただひとつ。
君の心がわたしの心臓といっしょに死んでくれれば、嬉しいの。