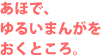
ておくれ
面白い奴が面白い事になった。
ただ、それだけのことだ。
「『その服似合わない』って、言われてしまいました…」
その声は沈んでいて、実際に頭をうなだれてみせる。その拍子に柔らかい色の髪が揺れた。
本人からしては上を向いていられないぐらいの絶望らしいが、こっちからしてみれば大したことではないように思える。だから少しの気も使わずに言いたいことをそのまま返事にした。
「確かにお前、センスないからな」
「えっ、そうだったんですか!?」
弾けたように顔を上げるものだから、黒い瞳とまっすぐ視線がぶつかって言葉に詰まる。いっしょに出かけたときに言ってくださいよだとか叫ぶので、知るかとだけ言っておいた。
このなんとも感情表現豊かな女は、小波美奈子といって、ひとつ年下の後輩だ。能天気で前向き。すぐすねるかわりにすぐ立ち直る。俺が吐く皮肉に呆れはするが気にはしない。それがこいつだ。
今までそんな奴は数える程度にしかいなかった。女ではこいつが初めてかもしれないというほどだ。少しうっとおしくて、かなり面白い。
歩いている道は海沿いで、静かな海は夕焼けに染まっていた。このごろは、とくにこいつと2人で帰る日が増えた。
その理由は分かっている。
「そうだ! 設楽先輩が服を選んでくれませんか?」
「はあ?」
突然なにを言い出すんだ、こいつは。名案だと目を輝かせる彼女を軽く睨む。
こいつはどうにもずれている。それを口に出せば先輩に言われたくないと反論されるのは目に見えているのでそうはしないが、少なくとも間違っている。
「設楽先輩、センスいいですし! ね、休みの日に行きましょうよ、お願いします!」
「…おまえ、俺を誘うんじゃなくてあいつを誘ったらどうなんだ。そのほうが好みも直接聞けるだろ」
「それにだって服を着て行かなくちゃじゃないですか! 似合わないって言われた服を着ていけません…」
へえ、俺とだったらいいのか。そう口を開きかけたが、見れば小波はがっくりと肩を落としている。
そうかやはり、こいつからしてみればそんなに重大なことなのか。
「…いつにするんだ」
そうひとつ口にすれば、ぱああと彼女の顔は明るくなった。エサを与えられた犬に似ている。
本当に表情がころころと変わって、面白い。
「…どうしました?」
不機嫌の色をわずかに滲ませ、彼女が尋ねてきた。思わず笑ってしまっていたらしい。
「いいや、なんでもない」
「…そうですか。それじゃあ、日曜にはばたき駅前で!」
頷いてみせると、彼女は微笑みで返してきた。夕焼けのオレンジに染まった、笑顔で。
「先輩、わたし、がんばります!」
「ああ、頑張れ」
発端となったのは、数ヶ月前。俺は、こいつの好きな奴を偶然によって知ったのだ。
そのころどうにも様子がおかしかったあいつから、その理由を問いただそうと家の前で待ち伏せれてみれば、彼女はあいつと並んで帰ってきた。
まさかそんな場面に出くわすとは思わなかったから、すぐさまその場を後にした。決して逃げたわけではない。
家に帰った後もどうしても気になってしまい電話をかけてみれば、話がある、なんて呼び出された。浜辺で彼女が言った内容はだいたい予想を外れず、外れた事といったらそれがこいつの一方的な片思いだということだ。
それからよく分からない成り行きで、俺は恋愛相談の相手をすることになった。恋愛なんて自分にもよく分からないから、こいつのを見てみるのも面白いかもななんて考えてる俺に向かって、彼女はこう言った。
「わたし、がんばりますね!」
その笑顔が、いろんなことが吹っ切れて軽くなったように見えたから。
「ああ、せいぜい頑張れ」
いつもどおりの皮肉を混ぜて、そう返した。
これがこのやり取りのいちばん最初で、もう何回も繰り返している。
「…いくらなんだって、買いすぎじゃあないのか」
彼女の元には、いくつもの紙袋が置いてあり、そのどれもに服やらなんやらがぎっしりと詰まっていた。
小波は紙袋を見た後に俺を見上げ、罰が悪そうに笑ってみせた。
「設楽先輩がわるいんです、先輩の選ぶ服のセンスがいいから、あれもこれも欲しくなってしまって…」
「人のせいにするな」
ひとつため息をついて、地面に置かれた紙袋のうちいくつかを掴んで歩き出す。すぐに後ろから慌てた声が追いかけてきた。
「せんぱい、にもつ、わるいです」
「バカ。この量をひとりで持てると思っているのか?」
体格のいいやつならまだわからないが少なくともこいつには無理だ。そう言うと、彼女は申し訳なさそうにありがとうございます、なんて言う。普段の態度とか、もっと失礼なものがあると思うのだが、へんなやつだ。
それからは、まあいつもと概ねおなじ。こいつの好きな奴についての話を聞きながら帰り道を歩いた。
さいきんメールが少なくなった気がするとか、自分がしすぎなんだろうかとか。次に会うときは、今日買った服のうちどれを着ていくだとか、どこに行こうだとか。
「遊園地…はちょっと寒いですかね、いまは」
「…さあ、構わないだろうがジェットコースターとかに乗るんなら短いスカートはやめておけよ」
「い、いつの話を…。めくれなかったじゃないですか!」
「次はわからないだろ。いいのか? あいつの前でそうなっても」
「……ズボンを履きます」
「ああ、そうしろ」
どれくらい前だったかか、こいつと2人で遊園地にいったときだ。あんなに短いスカートをはいていたくせに、ジェットコースターに乗る、なんて言い出すのでこいつはどうかしてると確信した。乗る乗らないで言い合いになって、それじゃあ乗ってみてめくれなかったらわたしの勝ち、めくれたら先輩の勝ちでどうですか!? だとか、いいだして…。色気のカケラもないというかそれ以前の問題だ。そうだ、そんなやつだから、夢にも思わなかったんだ、こいつが誰かに恋するだなんて。
だからといってなんだというわけでもない。もともとこいつは八方美人というべきか、誰にでもおんなじように笑いかけるから。こいつが、好きな奴にむけるそれだって似てるような気がしたんだ、「みんなだいすき」の延長みたいな。
…ほんとうに、そうだろうか?
この関係が始まった、あの日に見た、あいつの隣で笑う彼女。あの笑顔は、本当は、本当なら…。
「…あの、」
考えにふけっているところ、おずおずと、彼女が切り出す。
足を止めて小波を見ると、その視線は地面に向いていて。
「わたしには、設楽先輩だけです」
息が、止まった。
こいつは何を言っている。
「あのひとのこと、相談できるのなんて設楽先輩だけなんです。他の誰にも、女の子の友達にも、話せなくて。だから、こうやって話を聞いてくれて、アドバイスをしてくれて、…とてもうれしい」
いつも迷惑かけちゃってごめんなさい。眉を下げて彼女は笑う。
ああ、わかったよ、これからだっていくらでもしてやるから、だから。どうしてか、それ以上先の言葉を紡いでほしなくて、けれど制止の言葉も出てこない。だから彼女の言葉は続いていく。
「だからわたし、がんばります! 先輩が助けてくれたんだもの。先輩が、ともだちで、ほんとうによかった!」
あ。
ああ、そうか…。
笑う、彼女を見て、気づいてしまった。彼女の笑顔は、あの日から変わったのだ。
「…せんぱい? どうか、しました?」
返事をしない俺を、不安そうに小波が呼ぶ。だってそうだ、さっきの言葉はいつものやり取りだ。だから、俺も、定型の言葉を返さなければならない。
「…いいや、なんでもない」
彼女の目を見れず、視線を彼女の手の紙袋に落とす。
…そうだ、この会話も、この服も、
「……頑張れよ」
今見ている、この笑顔でさえも。
すべて、全てがあいつのものなのだ。いま、俺とこいつが2人でここにいる事実だって、あいつのためで。
…何を考えているんだ、俺は。どうだっていいことだ。だって俺は好きでこいつの手伝いをしているんだから。
まさか、……いや、ない! 万が一にもない! だってこいつだ、頭に花が咲いているようなやつだ!
そんなことを逡巡していれば、小波の家がもう目の前になっていた。小波は玄関に入っていこうとする。
「先輩、送ってくださってありがとうございます。それじゃあ…」
「おい」
…ん?
気づけば小波が黙ってこちらを見ている。
待て、いま、俺が呼び止めたのか? 用なんてないはずだ。いつもどおりに別れるだけなのに。
何かを言おうとした? こいつに、何かを? 何かって、だって、こいつは…。
「…あのう」
彼女はただ見つめるだけの俺に困ってしまったようだ。しかし俺だって困っている。なんなんだこれは、どうしろっていうんだ!!
「えっ、先輩!?」
焦った声の彼女に背を向け一気に駆け出した。なにも言える気がしなかったしなによりもこれ以上耐えられそうになかった。彼女の顔を、目を見るのも。声を聞くのですら。
わけがわからない。そもそもどうしてだ、どうして俺はこいつに協力しようなんて思ったんだ。
彼女が面白かったから? 恋愛事が珍しかったから? 間違いじゃあないが正解でもない。
その正解なんてもうとっくに知っていた。知っていたが認めるわけにはいかなかった。
認めてしまったら、すべてが駄目になってしまうだろうから。
次の日の学校で、小波は何事もなかったかのように俺に話しかけてきた。あんな別れ方をしてしまったのに、だ。
その事実に安心もしたが胸の内にどこか痛むものがあった。だってあんな別れ方をしたのがあいつだったら、と、こんなことであいつと自分を比べた。
彼女は放課後にいっしょに帰る約束だけとりつけて、友達のもとに去っていった。助かった、と思う。頭の中はぐちゃぐちゃで、あまり長く同じ場所にいれば何を言ってしまうか分からなかった。
(大丈夫だ、まだ、間に合う。手遅れなんかじゃない)
自分に言い聞かせる。大体あんなぼやーっとしたやつのどこがいい。よくない、断じてよくない!
そこまで考えて思い当たる。いつも笑っている彼女は、そう、どうしていつも笑っていられるのか。
片思いだっていうのに。片思いっていうのは辛いものじゃあないのか?
…きっと大丈夫なんだろう。彼女はなにかと弱音を吐くけれど、それはもうすでにカップルの喧嘩のように本人たちの世界が出来上がってるものなのかもしれない。そこにはもう、入り込める隙間なんてきっとない。
「…遅い」
下駄箱で彼女を待つこと、30分。普段の自分の性分から考えてこれだけ待てたのが奇跡というものだ。
まさか忘れたわけではあるまい。帰るにはどうやったって、下駄箱を通ることになるし。
まだ教室にでもいるのだろうか。遅れるならメールのひとつでも寄越せばいいのに。
「…見てくるか」
もしすれ違いになったらなったで、彼女のほうからメールでも電話でもしてくるだろう。自分のほうからするつもりもない。そうするなら直接会ったほうがよっぽど早い。
あいつの教室をのぞくと、思ったとおりに柔らかな色の髪をした後姿が見えた。窓際の席に座っている。
声をかけようとして、寸前で止めた。
机の上に置かれた彼女の手には携帯が握られていた。強く握りすぎているせいで指は白くなり、小刻みに震えていた。
その手の上に、ぽたり、滴が落ちた。ぽたり、ぽたり。滴は手の上に落ちて滑って流れていく。
その光景に息をのんで固まっていると、小波はこちらに気づいて振り返った。大きな目に涙が溜まっていた。
「……あ、せんぱい…」
へら、と情けない顔で彼女は笑ってみせる。目を細めた拍子に、溜まった涙が頬をつたった。
「ごめんなさい、約束してましたよね、すぐに…」
「…なんで」
言葉をさえぎる。どうしてだ。どうして、こいつは。
なにがあったのかは分からない。そんなに強く携帯を握り締めてる事の意味も、ひとり震えて泣いている理由も。
けれど、誰の事で泣いているぐらいかはわかる。当たり前だ。散々聞かされたのだ。だからそれは不思議でもない。
不思議なのは、わからないのは。
「なんで、笑うんだよ…」
声を押し出して呟くと、彼女の顔からすうと笑みが引いた。
だって俺は、こいつの相談役なんだ。好きな相手じゃあない。だから、無理に笑顔をつくって取り繕う必要なんて、ないのに。
なあ、どうすればいい。そんな笑顔が見たいんじゃあないし、ましてや泣き顔なんて見たくもない。
そんな顔が見たくて、俺はお前にアドバイスしてたんじゃあないんだ。そうだ、お前が今までとは違う顔で笑うから、だから俺はお前に協力することにしたんだ。
なのに、あいつはお前にそういう顔をさせないで、無理に笑わせ、こうやって泣かせてしまう。
だったら、俺は、どうしたらいい?
彼女は何事か言いかけ、止めて、顔を手で覆いかぶりを振る。
手を顔から離すと、椅子から立ち上がり、まっすぐにこちらの目を射抜いた。
「がんばりたいんです」
きらり、なみだが光る。
あのひとが、だれを想っていても、望みがなくったって、諦めたくないと。
彼女の涙が滲む言葉ひとつひとつに殺されて、壊されていく気がした。
言い訳も盾も、すべてが無駄に思えてしまって。
「わたし、がんばります、がんばりますから…」
いつのまにか彼女はうつむいて地面を向いていた。
いつものやり取りだ。飽きるほどに何回も繰り返してきたやり取りだ。だから俺も言葉を返さなければならない。がんばれ、といわなければならない。
返事を急かすように、彼女がうつむいたまま俺の制服の袖を掴んだ。だのに一向に声は喉の奥で押しとどめられ、出てくる気配が感じられない。
だから、もう、わかってしまった。認めるしかない。だってそうじゃないんなら、言ってしまえる筈だから。
彼女の腕を掴んで引いた。虚をつかれた彼女はなんなくこちらに倒れこみ、抱きとめる。腕の中で息をのんでいるのが感じ取れた。
彼女の背に手をまわす。彼女は抵抗こそしないが、こちらの背に手をまわすこともない。
それでも、もう、構わない。
そう思えてしまえるぐらいには。いいや、予感を感じたときにはもう、既に。
―― 手遅れに、なってしまっていたんだ。
ただ、それだけのことだ。
「『その服似合わない』って、言われてしまいました…」
その声は沈んでいて、実際に頭をうなだれてみせる。その拍子に柔らかい色の髪が揺れた。
本人からしては上を向いていられないぐらいの絶望らしいが、こっちからしてみれば大したことではないように思える。だから少しの気も使わずに言いたいことをそのまま返事にした。
「確かにお前、センスないからな」
「えっ、そうだったんですか!?」
弾けたように顔を上げるものだから、黒い瞳とまっすぐ視線がぶつかって言葉に詰まる。いっしょに出かけたときに言ってくださいよだとか叫ぶので、知るかとだけ言っておいた。
このなんとも感情表現豊かな女は、小波美奈子といって、ひとつ年下の後輩だ。能天気で前向き。すぐすねるかわりにすぐ立ち直る。俺が吐く皮肉に呆れはするが気にはしない。それがこいつだ。
今までそんな奴は数える程度にしかいなかった。女ではこいつが初めてかもしれないというほどだ。少しうっとおしくて、かなり面白い。
歩いている道は海沿いで、静かな海は夕焼けに染まっていた。このごろは、とくにこいつと2人で帰る日が増えた。
その理由は分かっている。
「そうだ! 設楽先輩が服を選んでくれませんか?」
「はあ?」
突然なにを言い出すんだ、こいつは。名案だと目を輝かせる彼女を軽く睨む。
こいつはどうにもずれている。それを口に出せば先輩に言われたくないと反論されるのは目に見えているのでそうはしないが、少なくとも間違っている。
「設楽先輩、センスいいですし! ね、休みの日に行きましょうよ、お願いします!」
「…おまえ、俺を誘うんじゃなくてあいつを誘ったらどうなんだ。そのほうが好みも直接聞けるだろ」
「それにだって服を着て行かなくちゃじゃないですか! 似合わないって言われた服を着ていけません…」
へえ、俺とだったらいいのか。そう口を開きかけたが、見れば小波はがっくりと肩を落としている。
そうかやはり、こいつからしてみればそんなに重大なことなのか。
「…いつにするんだ」
そうひとつ口にすれば、ぱああと彼女の顔は明るくなった。エサを与えられた犬に似ている。
本当に表情がころころと変わって、面白い。
「…どうしました?」
不機嫌の色をわずかに滲ませ、彼女が尋ねてきた。思わず笑ってしまっていたらしい。
「いいや、なんでもない」
「…そうですか。それじゃあ、日曜にはばたき駅前で!」
頷いてみせると、彼女は微笑みで返してきた。夕焼けのオレンジに染まった、笑顔で。
「先輩、わたし、がんばります!」
「ああ、頑張れ」
発端となったのは、数ヶ月前。俺は、こいつの好きな奴を偶然によって知ったのだ。
そのころどうにも様子がおかしかったあいつから、その理由を問いただそうと家の前で待ち伏せれてみれば、彼女はあいつと並んで帰ってきた。
まさかそんな場面に出くわすとは思わなかったから、すぐさまその場を後にした。決して逃げたわけではない。
家に帰った後もどうしても気になってしまい電話をかけてみれば、話がある、なんて呼び出された。浜辺で彼女が言った内容はだいたい予想を外れず、外れた事といったらそれがこいつの一方的な片思いだということだ。
それからよく分からない成り行きで、俺は恋愛相談の相手をすることになった。恋愛なんて自分にもよく分からないから、こいつのを見てみるのも面白いかもななんて考えてる俺に向かって、彼女はこう言った。
「わたし、がんばりますね!」
その笑顔が、いろんなことが吹っ切れて軽くなったように見えたから。
「ああ、せいぜい頑張れ」
いつもどおりの皮肉を混ぜて、そう返した。
これがこのやり取りのいちばん最初で、もう何回も繰り返している。
「…いくらなんだって、買いすぎじゃあないのか」
彼女の元には、いくつもの紙袋が置いてあり、そのどれもに服やらなんやらがぎっしりと詰まっていた。
小波は紙袋を見た後に俺を見上げ、罰が悪そうに笑ってみせた。
「設楽先輩がわるいんです、先輩の選ぶ服のセンスがいいから、あれもこれも欲しくなってしまって…」
「人のせいにするな」
ひとつため息をついて、地面に置かれた紙袋のうちいくつかを掴んで歩き出す。すぐに後ろから慌てた声が追いかけてきた。
「せんぱい、にもつ、わるいです」
「バカ。この量をひとりで持てると思っているのか?」
体格のいいやつならまだわからないが少なくともこいつには無理だ。そう言うと、彼女は申し訳なさそうにありがとうございます、なんて言う。普段の態度とか、もっと失礼なものがあると思うのだが、へんなやつだ。
それからは、まあいつもと概ねおなじ。こいつの好きな奴についての話を聞きながら帰り道を歩いた。
さいきんメールが少なくなった気がするとか、自分がしすぎなんだろうかとか。次に会うときは、今日買った服のうちどれを着ていくだとか、どこに行こうだとか。
「遊園地…はちょっと寒いですかね、いまは」
「…さあ、構わないだろうがジェットコースターとかに乗るんなら短いスカートはやめておけよ」
「い、いつの話を…。めくれなかったじゃないですか!」
「次はわからないだろ。いいのか? あいつの前でそうなっても」
「……ズボンを履きます」
「ああ、そうしろ」
どれくらい前だったかか、こいつと2人で遊園地にいったときだ。あんなに短いスカートをはいていたくせに、ジェットコースターに乗る、なんて言い出すのでこいつはどうかしてると確信した。乗る乗らないで言い合いになって、それじゃあ乗ってみてめくれなかったらわたしの勝ち、めくれたら先輩の勝ちでどうですか!? だとか、いいだして…。色気のカケラもないというかそれ以前の問題だ。そうだ、そんなやつだから、夢にも思わなかったんだ、こいつが誰かに恋するだなんて。
だからといってなんだというわけでもない。もともとこいつは八方美人というべきか、誰にでもおんなじように笑いかけるから。こいつが、好きな奴にむけるそれだって似てるような気がしたんだ、「みんなだいすき」の延長みたいな。
…ほんとうに、そうだろうか?
この関係が始まった、あの日に見た、あいつの隣で笑う彼女。あの笑顔は、本当は、本当なら…。
「…あの、」
考えにふけっているところ、おずおずと、彼女が切り出す。
足を止めて小波を見ると、その視線は地面に向いていて。
「わたしには、設楽先輩だけです」
息が、止まった。
こいつは何を言っている。
「あのひとのこと、相談できるのなんて設楽先輩だけなんです。他の誰にも、女の子の友達にも、話せなくて。だから、こうやって話を聞いてくれて、アドバイスをしてくれて、…とてもうれしい」
いつも迷惑かけちゃってごめんなさい。眉を下げて彼女は笑う。
ああ、わかったよ、これからだっていくらでもしてやるから、だから。どうしてか、それ以上先の言葉を紡いでほしなくて、けれど制止の言葉も出てこない。だから彼女の言葉は続いていく。
「だからわたし、がんばります! 先輩が助けてくれたんだもの。先輩が、ともだちで、ほんとうによかった!」
あ。
ああ、そうか…。
笑う、彼女を見て、気づいてしまった。彼女の笑顔は、あの日から変わったのだ。
「…せんぱい? どうか、しました?」
返事をしない俺を、不安そうに小波が呼ぶ。だってそうだ、さっきの言葉はいつものやり取りだ。だから、俺も、定型の言葉を返さなければならない。
「…いいや、なんでもない」
彼女の目を見れず、視線を彼女の手の紙袋に落とす。
…そうだ、この会話も、この服も、
「……頑張れよ」
今見ている、この笑顔でさえも。
すべて、全てがあいつのものなのだ。いま、俺とこいつが2人でここにいる事実だって、あいつのためで。
…何を考えているんだ、俺は。どうだっていいことだ。だって俺は好きでこいつの手伝いをしているんだから。
まさか、……いや、ない! 万が一にもない! だってこいつだ、頭に花が咲いているようなやつだ!
そんなことを逡巡していれば、小波の家がもう目の前になっていた。小波は玄関に入っていこうとする。
「先輩、送ってくださってありがとうございます。それじゃあ…」
「おい」
…ん?
気づけば小波が黙ってこちらを見ている。
待て、いま、俺が呼び止めたのか? 用なんてないはずだ。いつもどおりに別れるだけなのに。
何かを言おうとした? こいつに、何かを? 何かって、だって、こいつは…。
「…あのう」
彼女はただ見つめるだけの俺に困ってしまったようだ。しかし俺だって困っている。なんなんだこれは、どうしろっていうんだ!!
「えっ、先輩!?」
焦った声の彼女に背を向け一気に駆け出した。なにも言える気がしなかったしなによりもこれ以上耐えられそうになかった。彼女の顔を、目を見るのも。声を聞くのですら。
わけがわからない。そもそもどうしてだ、どうして俺はこいつに協力しようなんて思ったんだ。
彼女が面白かったから? 恋愛事が珍しかったから? 間違いじゃあないが正解でもない。
その正解なんてもうとっくに知っていた。知っていたが認めるわけにはいかなかった。
認めてしまったら、すべてが駄目になってしまうだろうから。
次の日の学校で、小波は何事もなかったかのように俺に話しかけてきた。あんな別れ方をしてしまったのに、だ。
その事実に安心もしたが胸の内にどこか痛むものがあった。だってあんな別れ方をしたのがあいつだったら、と、こんなことであいつと自分を比べた。
彼女は放課後にいっしょに帰る約束だけとりつけて、友達のもとに去っていった。助かった、と思う。頭の中はぐちゃぐちゃで、あまり長く同じ場所にいれば何を言ってしまうか分からなかった。
(大丈夫だ、まだ、間に合う。手遅れなんかじゃない)
自分に言い聞かせる。大体あんなぼやーっとしたやつのどこがいい。よくない、断じてよくない!
そこまで考えて思い当たる。いつも笑っている彼女は、そう、どうしていつも笑っていられるのか。
片思いだっていうのに。片思いっていうのは辛いものじゃあないのか?
…きっと大丈夫なんだろう。彼女はなにかと弱音を吐くけれど、それはもうすでにカップルの喧嘩のように本人たちの世界が出来上がってるものなのかもしれない。そこにはもう、入り込める隙間なんてきっとない。
「…遅い」
下駄箱で彼女を待つこと、30分。普段の自分の性分から考えてこれだけ待てたのが奇跡というものだ。
まさか忘れたわけではあるまい。帰るにはどうやったって、下駄箱を通ることになるし。
まだ教室にでもいるのだろうか。遅れるならメールのひとつでも寄越せばいいのに。
「…見てくるか」
もしすれ違いになったらなったで、彼女のほうからメールでも電話でもしてくるだろう。自分のほうからするつもりもない。そうするなら直接会ったほうがよっぽど早い。
あいつの教室をのぞくと、思ったとおりに柔らかな色の髪をした後姿が見えた。窓際の席に座っている。
声をかけようとして、寸前で止めた。
机の上に置かれた彼女の手には携帯が握られていた。強く握りすぎているせいで指は白くなり、小刻みに震えていた。
その手の上に、ぽたり、滴が落ちた。ぽたり、ぽたり。滴は手の上に落ちて滑って流れていく。
その光景に息をのんで固まっていると、小波はこちらに気づいて振り返った。大きな目に涙が溜まっていた。
「……あ、せんぱい…」
へら、と情けない顔で彼女は笑ってみせる。目を細めた拍子に、溜まった涙が頬をつたった。
「ごめんなさい、約束してましたよね、すぐに…」
「…なんで」
言葉をさえぎる。どうしてだ。どうして、こいつは。
なにがあったのかは分からない。そんなに強く携帯を握り締めてる事の意味も、ひとり震えて泣いている理由も。
けれど、誰の事で泣いているぐらいかはわかる。当たり前だ。散々聞かされたのだ。だからそれは不思議でもない。
不思議なのは、わからないのは。
「なんで、笑うんだよ…」
声を押し出して呟くと、彼女の顔からすうと笑みが引いた。
だって俺は、こいつの相談役なんだ。好きな相手じゃあない。だから、無理に笑顔をつくって取り繕う必要なんて、ないのに。
なあ、どうすればいい。そんな笑顔が見たいんじゃあないし、ましてや泣き顔なんて見たくもない。
そんな顔が見たくて、俺はお前にアドバイスしてたんじゃあないんだ。そうだ、お前が今までとは違う顔で笑うから、だから俺はお前に協力することにしたんだ。
なのに、あいつはお前にそういう顔をさせないで、無理に笑わせ、こうやって泣かせてしまう。
だったら、俺は、どうしたらいい?
彼女は何事か言いかけ、止めて、顔を手で覆いかぶりを振る。
手を顔から離すと、椅子から立ち上がり、まっすぐにこちらの目を射抜いた。
「がんばりたいんです」
きらり、なみだが光る。
あのひとが、だれを想っていても、望みがなくったって、諦めたくないと。
彼女の涙が滲む言葉ひとつひとつに殺されて、壊されていく気がした。
言い訳も盾も、すべてが無駄に思えてしまって。
「わたし、がんばります、がんばりますから…」
いつのまにか彼女はうつむいて地面を向いていた。
いつものやり取りだ。飽きるほどに何回も繰り返してきたやり取りだ。だから俺も言葉を返さなければならない。がんばれ、といわなければならない。
返事を急かすように、彼女がうつむいたまま俺の制服の袖を掴んだ。だのに一向に声は喉の奥で押しとどめられ、出てくる気配が感じられない。
だから、もう、わかってしまった。認めるしかない。だってそうじゃないんなら、言ってしまえる筈だから。
彼女の腕を掴んで引いた。虚をつかれた彼女はなんなくこちらに倒れこみ、抱きとめる。腕の中で息をのんでいるのが感じ取れた。
彼女の背に手をまわす。彼女は抵抗こそしないが、こちらの背に手をまわすこともない。
それでも、もう、構わない。
そう思えてしまえるぐらいには。いいや、予感を感じたときにはもう、既に。
―― 手遅れに、なってしまっていたんだ。