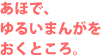
いじわる
「ねえ、君って料理とかできるひと?」
目の前の男の子が尋ねてきたのはそんなこと。
もうすぐ冬が終わる、けれどまだまだ外に吹く風は冷たい。そんな街中をわたしと赤城くんはふたりで歩いていた。
あと一ヶ月足らずで、わたしたちがそれぞれの高校から卒業して一年になる。それはつまり、わたしたちが気持ちを伝え合ってからも一年経つということだ。奇跡のような偶然でしか会えなかった彼が、必然にわたしの隣にいる。それがどうにも現実味がなく、顔を合わせるたびどこかほっとするような気持ちになっていた。
けれど今ではそんなこともない。違和感なく彼と笑いあえているし、彼の”余計なひとこと”にも大分慣れたものだ。毎回言い合いにはなるけれど、それは決して仲違いにまで発展することのない気さくなものだった。
「そうだなあ、ひ、人並みぐらいには…」
料理は出来るかと言う、赤城君の問いにどもりつつも答える。しかし、昔のわたしの料理の腕は、それはもう目も当てられないようなものだった。甘いものが好物であるお父さんに、父の日のプレゼントとしてケーキを作ってみればスポンジが爆発したし、それに生クリームを塗れば何故か煙が出てきて異臭がした。
また、高校一年生のバレンタイン。手作りチョコを渡したい相手と考えて、思い浮かぶ顔がないわけじゃあなくて、でもそれは当時どこの誰かも分からなかったから。だから作る気なんてなかったのだけれど、遊くんが言ったのだ、手作りのチョコが食べたいと。しかしその結果は悲惨なもので、溶けて固めるだけにも関わらず紫に変色しぼこぼこと泡を立て固まりやしなかった。それでも遊くんは、おねえちゃんの作ったものだからと食べてくれたけど…。
それからわたしは必死に料理の練習をした。お母さんに教えてもらったりなどしてレシピ通りにつくれるように頑張った。その甲斐あって、今はなんとか人並みぐらいには作れるようになっている。
わたしの答えを聞いて、赤城くんは微笑んで頷く。
「それじゃあ、大丈夫だね」
「なにが?」
「もうすぐじゃないか、忘れたのかい?」
そういわれて、彼が何を言おうとしているのかと思い至った。そうだ、もうテレビも町も、その話題でもちきりじゃあないか。2月14日。もうすぐなのだ。
気づいたものの、赤城くんの言い回しにかちんときた。まあ、それも、彼が言ってる事が図星だから、だけど…。素直に返事をするのがなんだか悔しくて、つい意地の悪い言葉を返す。
「あげるなんて、一言もいってないもの」
「くれないの?」
「さーあーねー」
半眼にして赤城くんを睨むけれど、彼は変わらず薄く笑んだままで、それがまたわたしの神経を逆撫でる。
「それに、赤城くん意地悪だもの。美味しくなかったらどうせ食べてくれないわ」
刺々しく言い放つと、赤城くんは眉間に皺を寄せた。
「そうとは言ってないだろ?」
「どうだか。それじゃあ大丈夫だねって、言ったでしょ? それって大丈夫じゃなかったら食べないってことじゃあないの?」
赤城くんが次の言葉を発する前に素早く言葉を被せる。
「ほんとうにいじわる。失敗したチョコでも、遊くんは食べてくれたのに…」
先程考えていたことと重なって、つい口に出してしまった。
ちなみに、失敗チョコを食べた遊くんはお腹を壊して寝込んでしまった。だから料理を練習したし、二度と失敗したものを人にあげたりしないと決めた。だから、チョコ作りに成功するにしろしないにしろ赤城くんに失敗チョコをあげるつもりはない。なので、失敗したら食べてくれないんでしょ、なんてその前提がありえないことなんだけど。ついつい嫌な事を言ってしまう。
「…ゆうくん」
「え?」
「へえ、ゆうくん、ね」
そう言う赤城くんの声には明らかに不機嫌な色が滲んでいる。顔を見てみれば、口の端は笑うみたいにもちあがっているのに目は全く笑っていない。ちょっと、嫌味なことをいいすぎたかな。でも、それにしてはちょっとヘンな気がする。
「チョコをあげてたんだ? 君は、そのゆうくんっていう人に」
「そう、だけど…」
「ふうん。それで、ゆうくんってのはどういう人なの?」
そこではたと気づいた。ああ、これはもしかして。
赤城くんは、遊くんが6つ下の男の子だと知らないのだ。それで誤解して、いらついている。 それに気づいたら、良くないことだけれど、少し愉快な気持ちになってしまって。
にこり、赤城くんに笑ってみせた。
「遊くんはね、すっごくいいひとなの!」
わざととびきり明るい声を出す。赤城くんの眉がぴくりと動いた。
「……へえ」
「とってもやさしくて、素直で、かわいいんだよ!」
「…そうなんだ」
「困ったことがあったらなんでも言ってくれて、だからすごくお世話になったの。チョコはそのお礼にあげたんだあ」
「………」
赤城くんが黙ってしまった。そろそろと顔色を伺うと、その背後には不穏なオーラが見えていた。
ちょっと、やりすぎちゃったかな。もうやめとこう。…怖い、し。誤解をとくために、遊くんは6つ下の男の子だと言おうと口を開く。
「あっ、でもね、遊くんは、むっ…」
「もういいよ」
言い終わる前に、突然腕を引かれた。気づいたら、すぐ鼻の先に赤城くんの顔がある。まっすぐに目を覗き込まれて言葉が出ない。こ、これは…。
「聞きたくない。今は、チョコをあげる相手なんて僕だけだろう?」
真剣な声だった。わたしの腕をつかむ手に痛いぐらい力がこもっている。顔が近くて、息がかかって、心臓がうるさい。かあっと顔に熱が集まるのが分かった。
「ご、ごめん…ね」
声を絞り出してやっと言えたのはそれだけだった。他にもいわないといけないことがあるはずだけれど、なにか余計な事を言ってしまうと、危ない気がした。主に距離とか、顔の近さとか。
赤城くんは小さくため息をついてわたしから顔を遠ざけた。けれど腕は掴んだままだ。
「…チョコ、くれるよね? 失敗しても、食べるから」
笑顔で凄まれて、小刻みにこくこくと頷いてみせる。
そうしたらようやく腕を離してくれて、代わりに手のひらを掴まれた。行こう、と言って歩き出す。
隣を歩く赤城くんの横顔を盗み見れば、まだ少し不機嫌な色が残っていて。
いけないのに、ちょっとだけ、笑ってしまった。
目の前の男の子が尋ねてきたのはそんなこと。
もうすぐ冬が終わる、けれどまだまだ外に吹く風は冷たい。そんな街中をわたしと赤城くんはふたりで歩いていた。
あと一ヶ月足らずで、わたしたちがそれぞれの高校から卒業して一年になる。それはつまり、わたしたちが気持ちを伝え合ってからも一年経つということだ。奇跡のような偶然でしか会えなかった彼が、必然にわたしの隣にいる。それがどうにも現実味がなく、顔を合わせるたびどこかほっとするような気持ちになっていた。
けれど今ではそんなこともない。違和感なく彼と笑いあえているし、彼の”余計なひとこと”にも大分慣れたものだ。毎回言い合いにはなるけれど、それは決して仲違いにまで発展することのない気さくなものだった。
「そうだなあ、ひ、人並みぐらいには…」
料理は出来るかと言う、赤城君の問いにどもりつつも答える。しかし、昔のわたしの料理の腕は、それはもう目も当てられないようなものだった。甘いものが好物であるお父さんに、父の日のプレゼントとしてケーキを作ってみればスポンジが爆発したし、それに生クリームを塗れば何故か煙が出てきて異臭がした。
また、高校一年生のバレンタイン。手作りチョコを渡したい相手と考えて、思い浮かぶ顔がないわけじゃあなくて、でもそれは当時どこの誰かも分からなかったから。だから作る気なんてなかったのだけれど、遊くんが言ったのだ、手作りのチョコが食べたいと。しかしその結果は悲惨なもので、溶けて固めるだけにも関わらず紫に変色しぼこぼこと泡を立て固まりやしなかった。それでも遊くんは、おねえちゃんの作ったものだからと食べてくれたけど…。
それからわたしは必死に料理の練習をした。お母さんに教えてもらったりなどしてレシピ通りにつくれるように頑張った。その甲斐あって、今はなんとか人並みぐらいには作れるようになっている。
わたしの答えを聞いて、赤城くんは微笑んで頷く。
「それじゃあ、大丈夫だね」
「なにが?」
「もうすぐじゃないか、忘れたのかい?」
そういわれて、彼が何を言おうとしているのかと思い至った。そうだ、もうテレビも町も、その話題でもちきりじゃあないか。2月14日。もうすぐなのだ。
気づいたものの、赤城くんの言い回しにかちんときた。まあ、それも、彼が言ってる事が図星だから、だけど…。素直に返事をするのがなんだか悔しくて、つい意地の悪い言葉を返す。
「あげるなんて、一言もいってないもの」
「くれないの?」
「さーあーねー」
半眼にして赤城くんを睨むけれど、彼は変わらず薄く笑んだままで、それがまたわたしの神経を逆撫でる。
「それに、赤城くん意地悪だもの。美味しくなかったらどうせ食べてくれないわ」
刺々しく言い放つと、赤城くんは眉間に皺を寄せた。
「そうとは言ってないだろ?」
「どうだか。それじゃあ大丈夫だねって、言ったでしょ? それって大丈夫じゃなかったら食べないってことじゃあないの?」
赤城くんが次の言葉を発する前に素早く言葉を被せる。
「ほんとうにいじわる。失敗したチョコでも、遊くんは食べてくれたのに…」
先程考えていたことと重なって、つい口に出してしまった。
ちなみに、失敗チョコを食べた遊くんはお腹を壊して寝込んでしまった。だから料理を練習したし、二度と失敗したものを人にあげたりしないと決めた。だから、チョコ作りに成功するにしろしないにしろ赤城くんに失敗チョコをあげるつもりはない。なので、失敗したら食べてくれないんでしょ、なんてその前提がありえないことなんだけど。ついつい嫌な事を言ってしまう。
「…ゆうくん」
「え?」
「へえ、ゆうくん、ね」
そう言う赤城くんの声には明らかに不機嫌な色が滲んでいる。顔を見てみれば、口の端は笑うみたいにもちあがっているのに目は全く笑っていない。ちょっと、嫌味なことをいいすぎたかな。でも、それにしてはちょっとヘンな気がする。
「チョコをあげてたんだ? 君は、そのゆうくんっていう人に」
「そう、だけど…」
「ふうん。それで、ゆうくんってのはどういう人なの?」
そこではたと気づいた。ああ、これはもしかして。
赤城くんは、遊くんが6つ下の男の子だと知らないのだ。それで誤解して、いらついている。 それに気づいたら、良くないことだけれど、少し愉快な気持ちになってしまって。
にこり、赤城くんに笑ってみせた。
「遊くんはね、すっごくいいひとなの!」
わざととびきり明るい声を出す。赤城くんの眉がぴくりと動いた。
「……へえ」
「とってもやさしくて、素直で、かわいいんだよ!」
「…そうなんだ」
「困ったことがあったらなんでも言ってくれて、だからすごくお世話になったの。チョコはそのお礼にあげたんだあ」
「………」
赤城くんが黙ってしまった。そろそろと顔色を伺うと、その背後には不穏なオーラが見えていた。
ちょっと、やりすぎちゃったかな。もうやめとこう。…怖い、し。誤解をとくために、遊くんは6つ下の男の子だと言おうと口を開く。
「あっ、でもね、遊くんは、むっ…」
「もういいよ」
言い終わる前に、突然腕を引かれた。気づいたら、すぐ鼻の先に赤城くんの顔がある。まっすぐに目を覗き込まれて言葉が出ない。こ、これは…。
「聞きたくない。今は、チョコをあげる相手なんて僕だけだろう?」
真剣な声だった。わたしの腕をつかむ手に痛いぐらい力がこもっている。顔が近くて、息がかかって、心臓がうるさい。かあっと顔に熱が集まるのが分かった。
「ご、ごめん…ね」
声を絞り出してやっと言えたのはそれだけだった。他にもいわないといけないことがあるはずだけれど、なにか余計な事を言ってしまうと、危ない気がした。主に距離とか、顔の近さとか。
赤城くんは小さくため息をついてわたしから顔を遠ざけた。けれど腕は掴んだままだ。
「…チョコ、くれるよね? 失敗しても、食べるから」
笑顔で凄まれて、小刻みにこくこくと頷いてみせる。
そうしたらようやく腕を離してくれて、代わりに手のひらを掴まれた。行こう、と言って歩き出す。
隣を歩く赤城くんの横顔を盗み見れば、まだ少し不機嫌な色が残っていて。
いけないのに、ちょっとだけ、笑ってしまった。